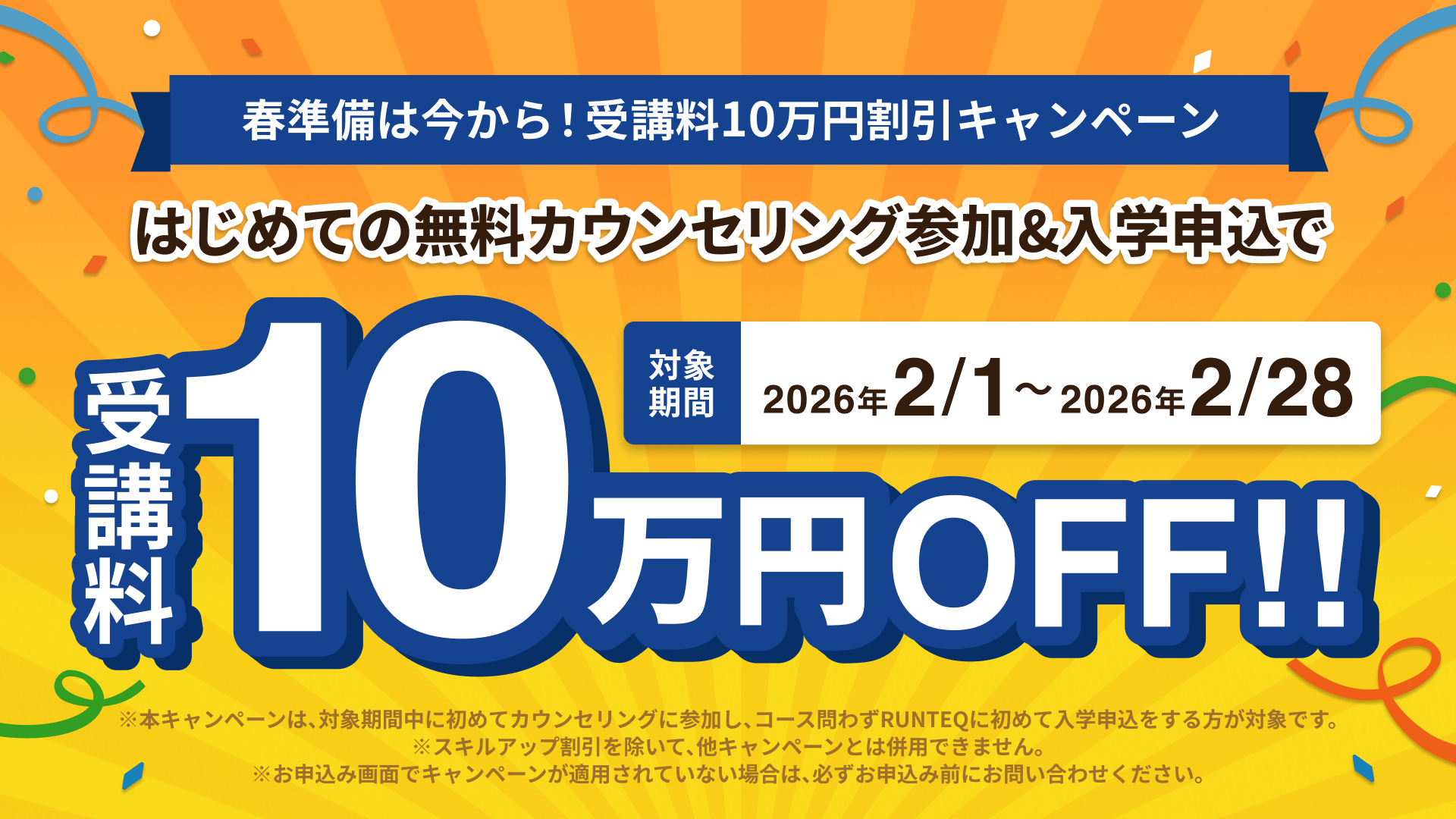株式会社Kaien様【企業インタビューvol.10】

今回は、「発達障害のある方の“凸凹の強み”を活かす」をミッションに、福祉・教育・就労支援の領域で多角的なサービスを展開されている株式会社Kaien様にインタビューさせていただきました!
同社は、代表のお子様が発達障害と診断された経験をきっかけに設立され、約15年にわたって、障害のある方の“働く力”や“幸福を追求する力”を高める支援を行っています。大人向けの就労支援をはじめ、18歳未満の子どもに向けた教育サービスや、求人サイト「マイナーリーグ」の運営など、多彩な取り組みで当事者の可能性を広げています。
インタビューでは、採用や事業の展望について近藤さん、技術面について山本さんにお話を伺いました。また、現在Kaienで活躍されているRUNTEQ卒業生・島田さんには、RUNTEQでの学びがどのように実務に活かされているかを語っていただきました。ぜひご覧ください。
福祉×ITで、人の可能性を広げる。多様性が力になる社会を目指して
――本日はよろしくお願いいたします。まず、貴社の事業内容について教えていただけますか?
近藤さん:私たちは、障害のある方の社会での活躍の場を広げることをミッションとして、約15年事業を続けている会社です。
主な事業としては、18歳以上の大人向け福祉サービスや、大学生・専門学生向けのサービスを提供しています。その他にも、18歳未満向けの教育サービスや、求人サイト「マイナーリーグ」の自社運営も行っています。社内ではkintone(キントーン)を導入し、DXも進めている状況です。
▼「マイナーリーグ」
障害特性への配慮を得ながらあなたの強みや専門性を活かせる仕事を見つける求人サイト。https://www.kaien-lab.com/job/mlgfi/

▼「ミッテル」
スキル習得と生活記録総合支援アプリ。
https://mittel.kaien-lab.com/career/index.html

📢 採用情報はこちらからもご覧いただけます:
https://corp.kaien-lab.com/recruit/recruit
エンジニア職をはじめ、Kaienではさまざまな職種で新しい仲間を募集しています。
「福祉×IT」という分野に興味がある方、社会課題の解決に技術で関わっていきたい方は、ぜひ採用情報をご確認ください!
「形にする力」と「事業への共感」が成長の鍵
――続いて、採用活動についてお伺いします。現在、エンジニア職の採用を継続されていると伺いました。募集職種の業務内容について教えてください。
山本さん: はい、エンジニア職の主な業務内容は、自社で運営する求人サイト「マイナーリーグ」と、もう一つのWebサービス「ミッテル」における機能追加や開発業務全般です。
その他、先ほど話に出たkintoneのカスタマイズなど、社内向けシステムの開発も担当していただきます。
――エンジニア職においては、学習したプログラミング言語と実務で使用する言語が異なる場合、不安を感じる方も多いと思います。その点について、言語の違いはどの程度問題になるのでしょうか?
山本さん: 私は、言語が違っていても本質的な理解ができていれば特に問題ないと考えています。
ただし、「学んだ内容を本当に理解しているかどうか」はとても重要で、たとえば自分の言葉で説明できるレベルの理解度が求められます。言語が違っても、基礎がしっかりしていれば置き換えは可能ですが、そこが曖昧だと、実務でかなり苦労することになります。
特に、これからはAIの進化に伴って、さまざまな言語に柔軟に対応していく必要がある時代になっていくと思うので、特定の言語にこだわりすぎず、幅広く視野を持って取り組める人材がより求められると感じています。
島田さん:私自身、RUNTEQでRubyを学びましたが、今はRubyを使っていないKaienで開発をしています。それでも、特別大きな壁を感じたことはありません。というのも、プログラミングにおける基本的な概念(たとえば型や配列など)は言語が違っても共通している部分が多いからです。
逆に言えば、そういった基礎的な考え方や構造をしっかりと理解していることが大切なんだと思います。
――採用時に重視されているポイントは何ですか?
近藤さん: 私たちは「福祉事業」を展開し、「障害のある方の社会での活躍を支える」というミッションを掲げている会社です。そのため、まずは当社の事業内容に共感し、興味を持ってくれることを非常に重視しています。
また、当社はベンチャー気質でフラットな組織です。事業部のメンバーとエンジニアの距離が非常に近いため、自分で考えて主体的に動ける力は、採用においてとても重要なポイントですね。
山本さん: 技術面では、事業部と話をして何かを作る機会が多いため、実際に手を動かして何かを形にできる力はとても大切だと考えています。学習して知識を持っているだけでなく、それを実践してアウトプットした経験があるかも重視しています。
コミュニケーション面では、事業部との対話の中で「何から取り組んでいくか」を一緒に考えることも多いため、課題を共有し、優先順位をつけながら進められるような対話力も重要ですね。「何が大事なのか」を話し合えるようなコミュニケーション能力があると、非常に良い印象を受けます。
そのため、ポートフォリオは必ず拝見しており、「どのような課題にチャレンジしているか」という点は特に注目しています。
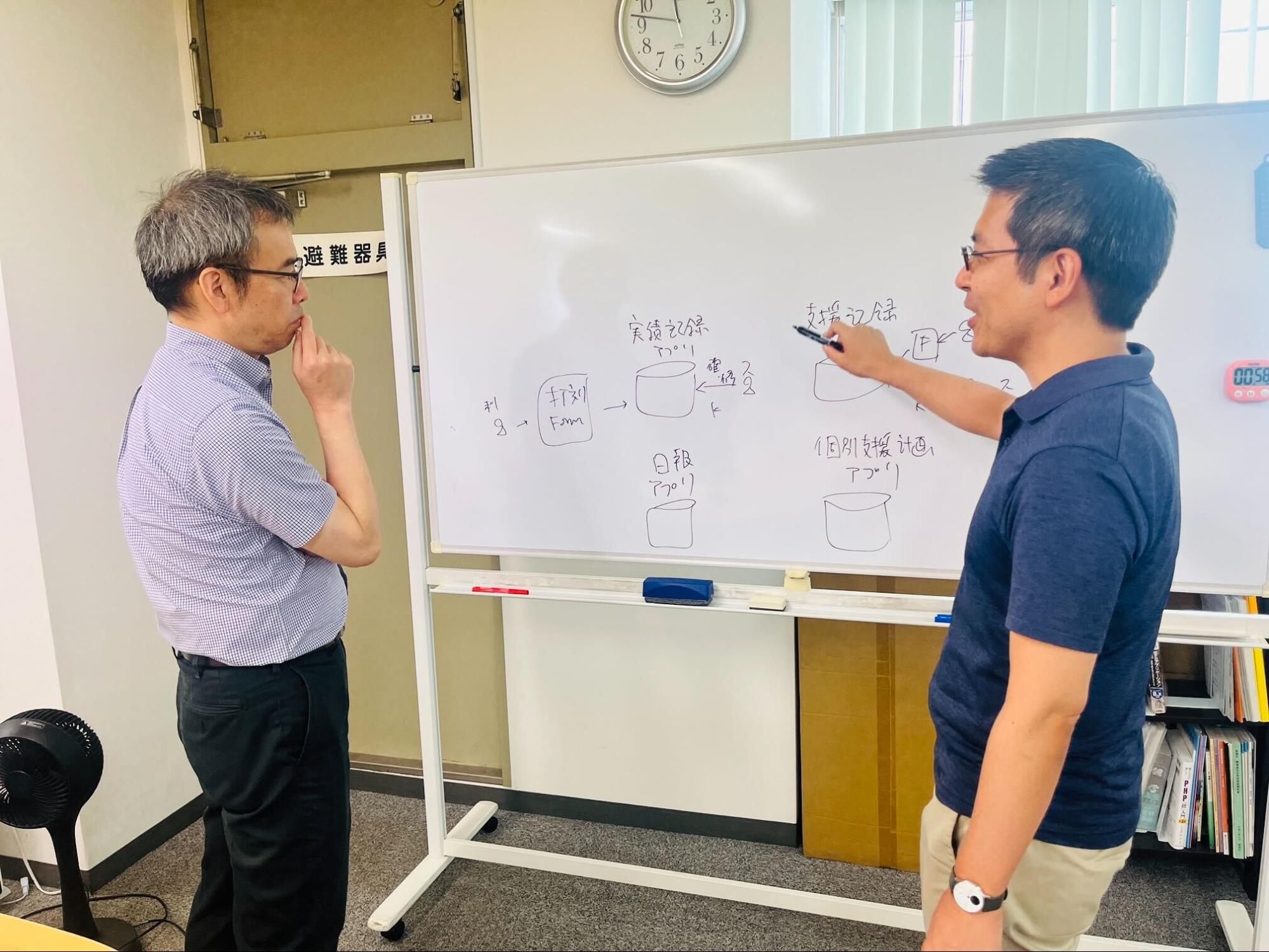 (写真左:山本さん/写真右:近藤さん)
(写真左:山本さん/写真右:近藤さん)
――未経験で入社された場合の教育体制について教えてください。
近藤さん:実は、かしこまった研修制度や一定期間の研修カリキュラムのようなものは、特に設けておらず、入社後すぐに、実際の開発に携わっていただくスタイルをとっています。
ポートフォリオを作成している方であっても、実務経験がないのは当然だと考えているため、質問しやすい雰囲気づくりは常に意識しています。もちろん、いきなりすべてを一人で任せることはなく、個人のスキルや経験に合わせて、無理のない範囲でタスクを割り振るよう配慮しています。
また、当社は開発部門と事業部門の距離が非常に近いことが特徴で、わからないことがあればすぐに相談できる環境です。一人で抱え込まずに済むようなサポート体制を整えていますので、安心して取り組んでいただけると思います。
最近では、社外での学びの機会を積極的に設けており、直近ではAWSサミットへの参加など、メンバーの成長を後押しする取り組みも行っています。
――質問しやすい環境が整っているとのことですが、実際に島田さんが入社された際も、そうした雰囲気は感じられましたか?
島田さん:そうですね、朝会のミーティング後などに、先輩社員の方が「山本さん、ちょっとお時間いただけますか?」といった感じで相談している場面をよく目にしていました。そういった様子を見て、「自分もこのタイミングで聞いていいんだな」と感じて、自然と質問しやすい雰囲気がありました。
何より印象的だったのは、入社してすぐに山本さんから「同じこと何回聞いてもいいからね」と声をかけていただいたことです。この一言が、自分の中ではとても大きな安心材料になりました。本当に相談しやすい環境が整っていると、今でも実感しています。
――御社の採用ページで、「管理職がいない自律的な人事制度」と紹介されていた点が印象的でした。実際に働かれてみて、そのような組織体制や風土を感じる場面があれば、ぜひ教えていただけますか?
近藤さん:情報の透明性はとても高くて、自分からアクセスすれば、数字を拾って調べることもできますし、情報がオープンにされていると感じています。
私自身、以前はもう少し規模の大きい会社にいたのですが、そのときは何か提案を進めるにも、いくつもの承認を通さないといけなかったり、「この人の顔色をうかがっておいた方がいい」といった空気が、多少なりともあったんですよね。
一方で今の会社では、そういった社内政治のようなものはほとんど感じません。
「正しいことは正しい」とちゃんと判断される環境がある、という感覚が強くあって、そこにすごく安心感を覚えています。
そういう意味でも、本当にフラットな組織だなと実感しています。
山本さん:私自身も、「役職がないから発言権がない」といったような感覚は全くありません。むしろ、「自分はこの役割だから、こういう視点で意見を出す」といった役割ベースでの発言や判断が尊重されていると感じています。
役職や上下関係ではなく、役割に基づいてフラットに議論できる環境があるというのは、この会社の大きな特長だと思います。
「話してみたい」と思わせるポートフォリオから、現場で信頼される存在へ
――島田さんはRUNTEQのご卒業生とのことですが、採用の際に特に印象に残った点があれば教えてください。
近藤さん:採用の場面では、候補者の方が作成されたポートフォリオを拝見していますが、島田さんのポートフォリオは、UIが凝らされていて、画面を見たときに「お話したいな」と思ったのが第一印象ですね。 なぜそのような画面設計にしたのか、といった意図も気になりました。
ソースコードに関しては細かく見るわけではありませんが、使用している言語やライブラリ、どこにデプロイしているのかなど、「何か新しいことにチャレンジしているのかな」といった観点ではチェックしていますね。
――実際に一緒に働かれてみて、島田さんの強みはどんなところにあると感じましたか?
近藤さん: 島田さんは、まだ入社して1カ月ほどのタイミングから、社内システムの一部について「このチームの人に聞きながらやってみて」といった、比較的粒度の大きいタスクをお任せしていたのですが、しっかりと関係者にヒアリングをしながら、必要に応じてシステムチームのメンバーにも助けを求めて、きちんと進めてくれました。
そういった必要な場面で助けを求める力や、自ら積極的に動く姿勢はとても頼もしく感じましたね。
これは私だけでなく、実際に島田さんとやり取りをしていた現場のメンバーからも、「まだ入社して1カ月とは思えない業務理解度ですね」と高く評価する声が上がっていました。
また最近では、採用活動にも積極的に関わってくれていて、フレッシュな目線で意見を出してくれるなど、採用面での発信にも前向きに取り組んでくれています。
 (写真左:島田さん/写真右:山本さん)
(写真左:島田さん/写真右:山本さん)
――素晴らしいですね!島田さんご自身で何か意識していることはありますか?
島田さん: わからないことは、その場ですぐに聞くことを意識しています。
入社して1〜2カ月目の頃は、「あとで聞けばいいか」と後回しにしてしまうこともあったのですが、結果的にその方がコミュニケーションのやり取りが増えて、かえって時間がかかることに気づきました。
最近では、実装の依頼を受けた際に、ミーティングの場などで疑問点を残さずその場で解消することで、スムーズに作業に取りかかれるようになったと実感しています。
――島田さんが入社されてから、チームの中でどんな変化がありましたか?
近藤さん: 当社のエンジニアチームでは、それまでは「事業部の人に話を聞きに行く」という動きに対して、「これって自分から聞きに行っていいのかな?」とか、「本当にこんなことを聞いてもいいのかな?」やや一歩引いた姿勢のメンバーも多かった印象でした。
そのため、私や山本のほうである程度ヒアリングを先に行い、それをタスクに落とし込んでから「じゃあこれをやってみようか」と依頼するような進め方が多かったんです。
ただ、当社として本来目指しているカルチャーは、一人ひとりが主体的に動いて、疑問を持ったら自分からどんどん聞きに行き、解消しながら前に進んでいくというスタイルです。
その意味で、島田さんはまさにそれを体現してくれている存在だと思っています。
実際、島田さんの行動に触発されて、チーム内でも「自分から動いて質問する」という動きが少しずつ増えてきた感触があり、チーム全体が活性化してきていると感じます。そういった意味でも、島田さんの存在は非常に良い刺激になっていると思います。
エンジニアは、“人間らしい仕事”に集中できるように環境を整えること
――島田さんの現在の業務内容について教えてください。
島田さん:現在は、当社が提供している「就職サポート」および「就職後の定着サポート」に関する業務に携わっています。
これらのサービスは各拠点にリーダーの方がいらっしゃるのですが、そのリーダーの方々が業務をより効率的に進められるように、kintoneのカスタマイズを行うことが今のタスクです。
具体的には、業務のどの部分を効率化できそうかをリーダーの方と相談しながら見つけていき、実際にカスタマイズを試作して「こういった形でどうでしょうか?」とフィードバックをもらいながら改善を進めています。
現場の声を取り入れながら、業務に寄り添った改善提案と実装を繰り返すような形で取り組んでいます。
――現在の業務で、やりがいを感じるのはどんな瞬間ですか?
島田さん: 現場で働いている方々から「この作業が大変」「もっと効率化したい」といった課題を伺い、それに対して「こうすれば解決できるかもしれません」と提案できる瞬間にやりがいを感じます。
たとえば最近は、PDFをKintoneにアップロードすると、AIが内容を読み取って自動で要約してくれる機能を実装しました。それを実際に使っていただいた際に、 「これができたら、いろんなことがすごく楽になるね」という反応をもらえて、本当にうれしかったです。
――実際にエンジニアとして働く中で、どんなところに魅力を感じていますか?
島田さん: 最近特に感じているのは、現場の方やさまざまな人たちが、“人間らしい仕事”に集中できるように環境を整えることが、エンジニアの役割であり、大きな魅力だということです。
たとえば、PDFの内容を手作業で転記するような業務は、必ずしも人間がやるべき仕事ではないと思っています。
そうした作業にエンジニアが介在することで、その時間を削減できて、その分「利用者の方としっかりコミュニケーションを取る」ことや、「事業をより良くするためのアイデアを考える」といった本質的な仕事に時間を使えるようになると思います。
そうした“価値ある時間”を生み出す手助けができるというのが、エンジニアという仕事の一番の魅力だと思います。
――エンジニアの仕事に対して、入社前のイメージとのギャップはありますか?
島田さん:大きなギャップがあったわけではないのですが、入社してから、コードを書く時間よりも、人とコミュニケーションを取ったり、課題解決の方法を考えたりする時間の方が多いことに気づきました。
たとえば、事業部の方や現場の方にヒアリングをして、「こういうことに困っているんだ」と理解した上で、「では、どうすればその課題を解決できるか?」をじっくり考える時間がかなり多いんです。
ただ、その時間がつらいとか大変だと感じることはなくて、むしろそこから得られるやりがいも大きいと感じています。
なので、イメージとのギャップというよりは、「思っていた以上に人との関わりが多い仕事なんだな」という発見があった、という感覚です。
作ったものに反応が返ってくる喜びを実感。仲間と学び合えたRUNTEQ生活
――RUNTEQでの学習期間を振り返って、「これは少し大変だったな」と感じる場面はありましたか?
島田さん:正直、大変だったと感じることはあまりなかったです。
もともとものづくりやプログラミングの中で、エラーを解消していく過程そのものを楽しめる性格なので、「プログラミングの勉強がつらい」というような感覚はありませんでした。
強いて挙げるとすれば、自分の作りたいものではなく、カリキュラムに沿った内容を学習していくことに対して、時々モチベーションが上がらない場面はありました。
それでも、「このカリキュラムで学んだことを活かして、自分の好きなものを作ってみよう」と思えることで、最終的にはモチベーションを保つことができました。
目的意識を持って取り組むことができたので、結果的に楽しく続けられたのかなと思っています。
――反対に、「これは楽しかった!」と印象に残っている出来事や瞬間があれば教えてください。
島田さん:自分が作ったアプリを必ず周りの受講生が触ってくれる環境というのは、すごく楽しかったですね。
フィードバックをもらえたり、「これ面白いね」とか「どうやって作ってるの?」といった感想をもらえることが、アプリを作ってよかったと実感できる瞬間でした。そういったやり取りを通して、作ったものに反応が返ってくる喜びや、誰かに届くことの楽しさを強く感じました。
それは、やっぱりコミュニティがあったからこそ味わえたやりがいだったと思います。
――カリキュラム以外でRUNTEQのコミュニティも活用されていたんですね!
島田さん:はい、かなり活用していました。たとえば、Discordに参加して、他の受講生と一緒に勉強する機会も多かったですし、夜に毎日開催されていた「アウトプット会」にも積極的に参加していました。
そのアウトプット会では、自分が学んだことを発信するだけでなく、他の方の発信から新たな学びを得ることもできる、とてもよい機会になっていました。
一方通行ではなく、双方向で学び合える環境として、すごく有効に活用していたと思います。
――現在の業務で、RUNTEQでの学びが活かされていると感じることはありますか?
島田さん: プログラミングの基礎知識はもちろんですが、それ以上に「エンジニアとしてチームで働く上での知識」が非常に役立っていると感じています。
例えば、弊社ではバージョン管理にBitbucketを使っていますが、RUNTEQでGitの基本的な使い方や概念を学んでいたおかげで、専門用語がわからず困るようなことはありませんでした。
また、業務で使っているコミュニケーションツールも、RUNTEQで使用していたツールと似ていたため、スムーズに業務に馴染むことができた点も大きかったと思います。
――現在も学習を継続されているそうですが、どのようなことに取り組んでいますか?
島田さん: 今は、基本情報技術者試験の取得に向けて勉強しています。また、RUNTEQを受講していた頃と比べて、最近は趣味の時間にも技術記事を読むことが増えました。
受講中と違うのは、今は実際の現場に「この問題を解決したい」という具体的な課題があるということです。その課題を前にして、「どうやったらこれを解決できるかな?」という視点で技術記事を読むのがすごく楽しくて、それが大きな変化のひとつだと感じています。
基本情報技術者試験については、RUNTEQ時代の同期が受験すると話していたのを聞いて、自分も感化されてチャレンジしようと思いました。RUNTEQ卒業後も、同期や他の受講生とのつながりは続いていて、むしろ卒業してからのほうが会う機会が増えた人もいるくらいです。
「あの人が頑張っているから、自分も頑張ろう」と、良い刺激をもらいながら日々学習に取り組んでいます。
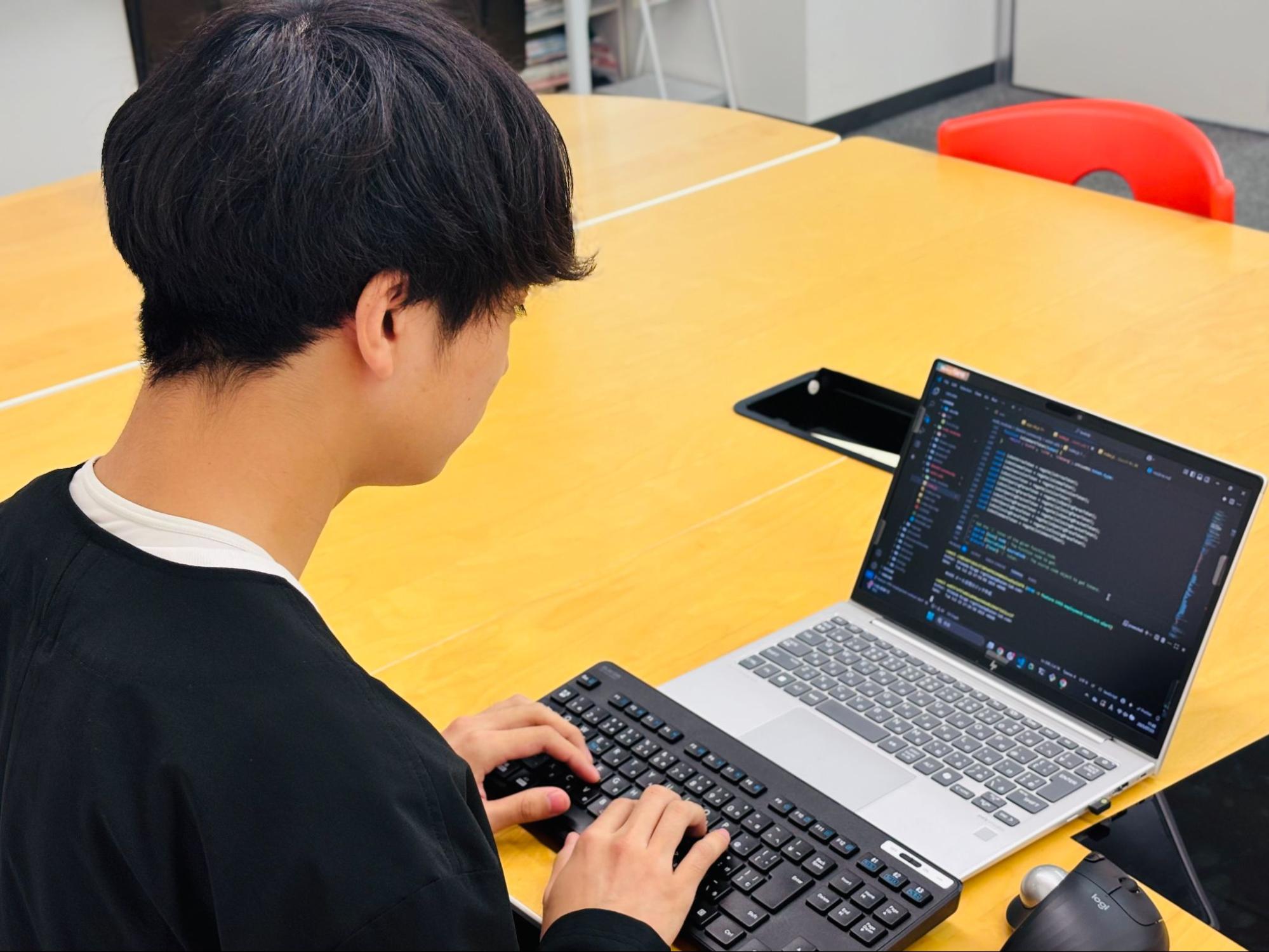 (エンジニア 島田さん)
(エンジニア 島田さん)
――最後に、貴社への応募を検討している方に向けて、メッセージをお願いします!
近藤さん:当社は、規模としてはまだ小さな会社ですが、そのぶん組織がフラットで風通しが良く、スピード感を持って挑戦できる環境があります。
AIをはじめとした新しい技術にも積極的に取り組んでいるため、そういった分野に興味がある方にとっては、まさに実践を通じてスキルを磨き、ビジネスの中で価値を生み出す経験がすぐにできる職場だと思います。
また、当社は福祉領域を中心とした事業を展開しており、社会貢献性の高い取り組みに関われる点も大きな魅力です。
「技術力を高めたい」という想いと、「社会に貢献したい」という気持ちの両方を大切にできる環境がここにはあります。
この2つの軸にやりがいや面白さを感じていただける方と、ぜひ一緒に働けることを楽しみにしています。
島田さん: 本当にフラットな組織だなというのは、日々強く感じています。
代表にも役職名ではなく「さん付け」で呼んでいいという文化があって、そういった距離の近さがすごく印象的でした。
自分が面接を受けていたときは、福祉の会社ということで、もっと堅い雰囲気なのかなと思っていたんですが、実際に入社してみると、思っていた以上にフラットで、スピード感があり、改革意識も強く根付いている会社だと感じています。
本日はお忙しい中ありがとうございました。
御社のさらなるご発展と、皆様のご活躍を心よりお祈りしております!
編集後記
本インタビューでは、株式会社Kaienの近藤さん、山本さん、そしてRUNTEQ卒業生の島田さんにお話を伺い、同社の採用・技術・チームの在り方について多角的にお聞きすることができました。
「福祉×IT」というユニークな領域で社会課題の解決に真摯に取り組む姿勢と、社員一人ひとりの主体性を尊重するフラットな企業文化が非常に印象的でした。特に、採用において「事業への共感」と「形にする力」を重視するというお話は、これからエンジニアを目指す方々にとって大きなヒントになったのではないでしょうか。
そして、島田さんが話していた「エンジニアは、人間らしい仕事に集中できるように環境を整える存在」という考え方も印象的でした。
ただコードを書くのではなく、現場の声に耳を傾けながら、技術を使って業務の負担を減らしていく。そういった姿勢が、まさに今の現場で求められているエンジニアの在り方なのだと感じました。
もしあなたが、「本気でエンジニアになりたい」「企業から本当に求められるスキルを身につけたい」と考えているなら、一度RUNTEQの無料カウンセリングで話を聞いてみませんか?
あなたのエンジニアとしての第一歩を、心から応援しています。