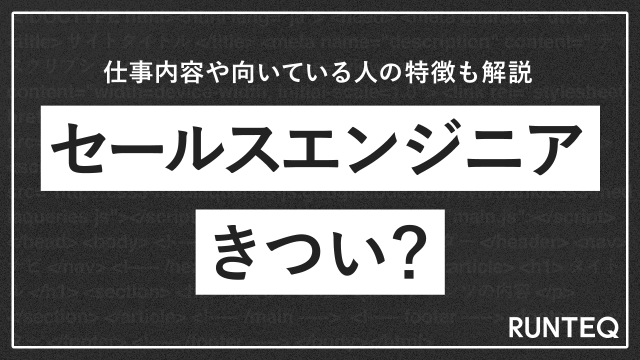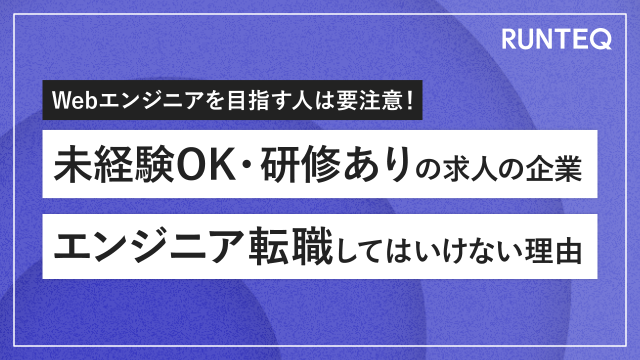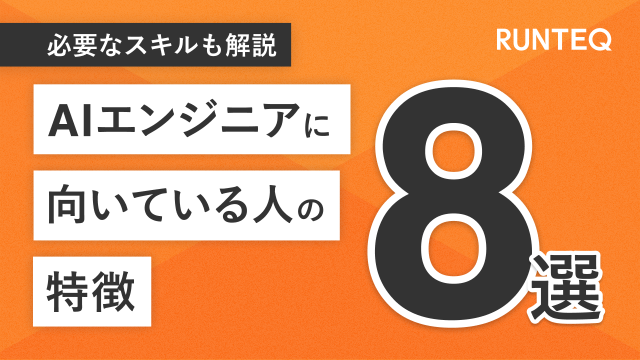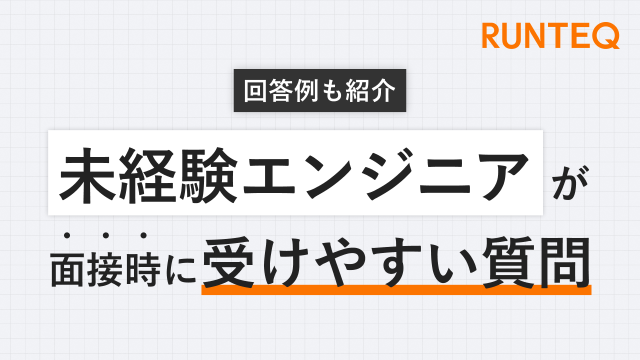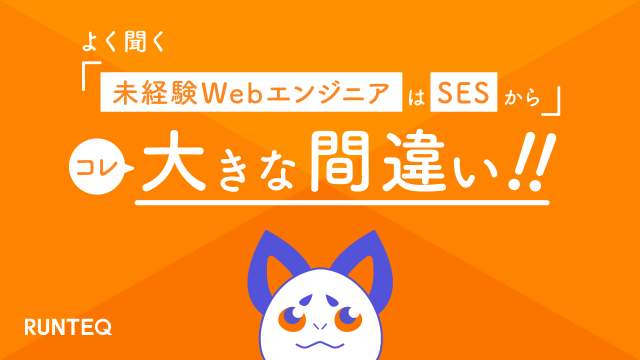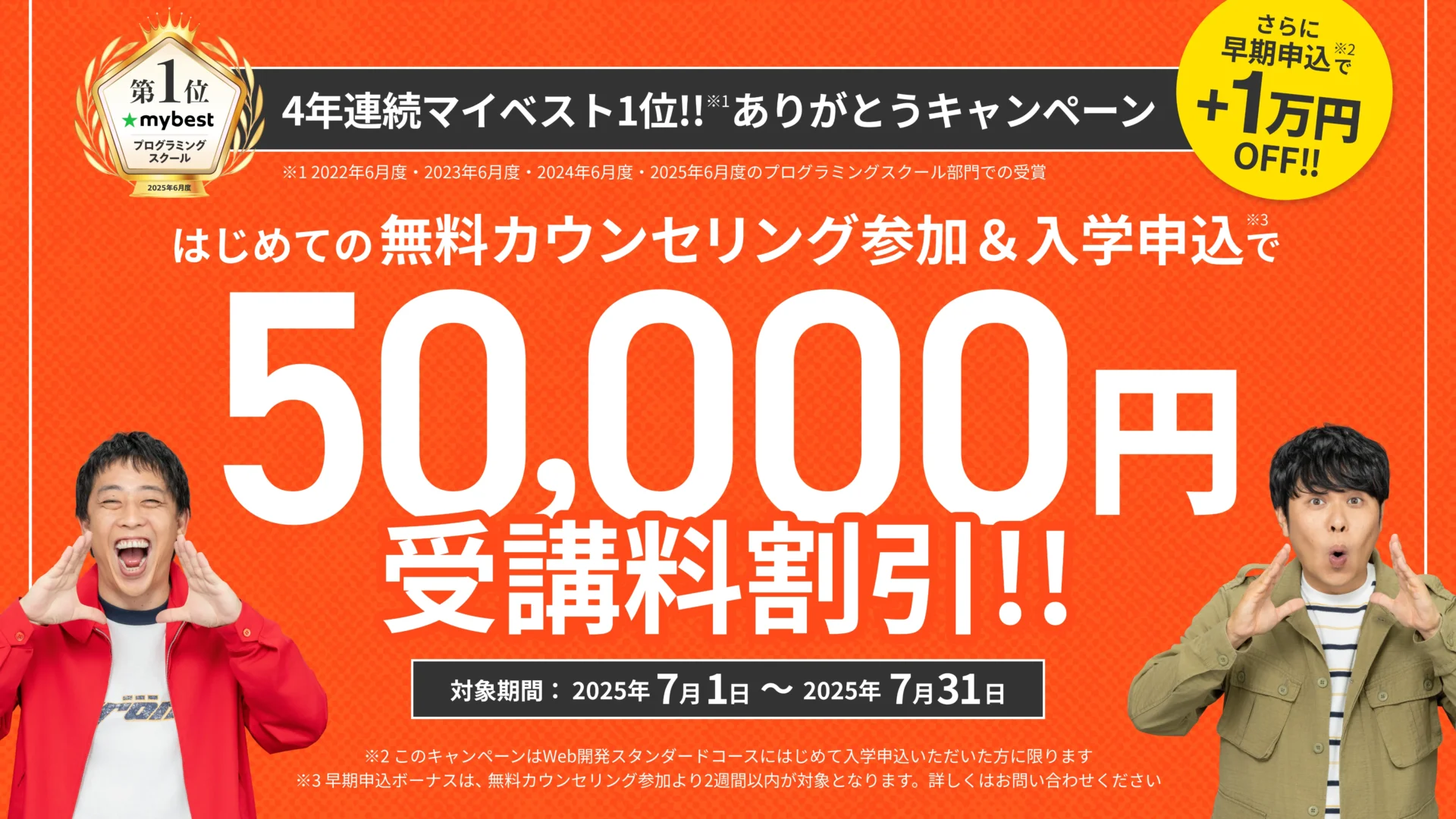「インフラエンジニアの将来性ってどう?需要は高い?」
「インフラエンジニアのキャリアパスは?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
インフラエンジニアと聞くと、「夜勤が多い」「急なトラブルに対応をしないといけない」など、他のエンジニアと比べて大変な印象を持っている人もいるでしょう。
そこで今回は、下記の内容を解説していきます。
- インフラエンジニアの需要や将来性
- インフラエンジニアの仕事内容や働き方
- インフラエンジニアのキャリアパス
- インフラエンジニアがキャリアアップするために必要な4つのスキル
インフラエンジニアに将来性がある理由

結論からお伝えしますと、インフラエンジニアの需要や将来性は高いと言えます。
その主な理由としては、以下の4つです。
- 需要が高く求人数も多い
- クラウド化の普及
- インフラの構築・保守・運用の仕事はなくならない
時代の変化により求められるスキルなども変わりますが、根本としてインフラエンジニアの需要は高いままでしょう。
その理由について1つずつ詳しく解説していきます。
需要が高く求人数も多い
インフラエンジニアの需要は以前も今も高いままで、常に多くの求人があります。
例えばIT人材専門の求人サイトである「レバテックキャリア」にてインフラエンジニアの求人を検索してみると、2,111件もヒットします。(2023年11月時点)
他のエンジニア職の多くが数百件程度の求人であるため、インフラエンジニアの求人数はかなり多いと言えます。
今や、あらゆる企業においてネットワーク環境は必須となっているため、サーバーやネットワークといったインフラ関連の構築・保守・運用の仕事がなくなることはまずあり得ないでしょう。
さらには、企業がIT化やDX化の推進を図っているため、IT人材の需要自体どんどん高まっています。
実際に「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」では2030年にはIT人材が最大約79万人も不足するという結果が出ています。
これだけIT人材の需要が高いのですから、システムの根幹を支えるインフラエンジニアの需要もさらに高まっていくことが予想されます。
クラウド化の普及
インフラエンジニアはもともと需要が高く将来性のある職種ですが、近年では「オンプレミス」から「クラウド」への移行が進んでいるため、さらに需要が高まると思われます。
- コストが削減できる
- 構築スピードが速い
- 運用管理の負担を削減できる
- 時間や場所を選ばず利用できる
クラウド化の具体例として、Amazonが提供するAWSや、Microsoftが提供するAzureなどのパブリッククラウドを導入する企業が増えています。
そのため、今後はクラウドに関する知識も必要になってくるでしょう。
もちろん、オンプレミス環境のままの企業もたくさん残っていますが、市場の流れに乗りクラウド化へ対応できるスキルがあると、市場価値の高いエンジニアになれます。
インフラの構築・保守・運用の仕事はなくならない
クラウドが普及することにより、インフラエンジニアに求められるスキルは大きく変わりました。
しかし形は変わっても、ITインフラの構築や保守運用などの仕事は、引き続きなくなることはありません。
インフラの仕事でも、クラウドに関しては「クラウドエンジニア」という新しい職種が誕生していますが、従来のインフラエンジニアの存在もまだまだ必要です。
クラウド化が徐々に進んでいる今現在でも、多くの企業がオンプレミス環境で業務システムや自社サービスを運用しているため、その保守・運用の仕事を担当するエンジニアは必要なのです。
企業によっては、様々な理由からクラウド化が難しいという事情もあります。
こういった理由から、従来のインフラエンジニアの将来性はまだまだ高いままだと考えて問題ないでしょう。
インフラエンジニアの仕事内容

この項目では、インフラエンジニアの具体的な仕事内容について詳しく解説していきます。
主な仕事内容は3種類
インフラエンジニアの仕事内容としては、大きく分類すると設計・構築・保守運用の3つに分かれます。
- 設計:構築したいインフラ環境の全体図を作成する
- 構築:設計書をもとにサーバーやネットワーク機器の設置や設定を行う
- 保守運用:出来上がったインフラが安全に動作するように監視し、問題が起これば対処する
いずれの仕事も、上流工程(要件定義・設計・構築)と下流工程(運用・保守・監視)に分かれており、最初は下流工程で経験を積んだ後に、上流工程も担当できるようになっていくのがインフラエンジニアとしての一般的なキャリアップの流れとなるでしょう。
インフラエンジニアの種類
インフラエンジニアは、担当する業務内容によって下記のように種類が分かれます。
- サーバーエンジニア:サーバーの構築・運用・保守や、他の機器とケーブルをつなぐような物理的な作業も行う
- ネットワークエンジニア:安全かつ安定したネットワークシステムの設計・構築・運用・保守を行う
- セキュリティエンジニア:情報セキュリティに特化しており、外部からのIT攻撃などの対策を行う
- クラウドエンジニア:AWS(Amazon Web Service)やGCP(Google Cloud Platform)などのクラウド環境下におけるシステムの開発・運用管理・保守を専門に行う
- データベースエンジニア:大量のデータ処理に耐えられるように、データベースの設計やチューニングを行う
大企業などで採用されやすいオンプレミス
オンプレミスとは、サーバーやソフトウェアをゼロから自社で組み上げていく構築方法で、いわゆる自社運用といった形になります。
- 自社で構築するためシステムをカスタマイズしやすい
- 自社システムと連携しやすい
- 第三者が入りづらく安全性が高い
- 自社で全て用意するため初期コストが高い
- 構築に時間がかかる
- トラブルが起きたときは自社で対応しないといけない
自社運用のためカスタマイズ性が高い反面、コスト面やトラブルが起きた時も全て自社で対応しないといけないデメリットがあります。
スタートアップで採用されやすいクラウド
近年では、自社で運用するオンプレミスよりも普及しているのが「クラウド」です。
コストが低く、導入のための準備が少ないため、スタートアップ企業では採用されやすいです。
クラウドでインフラを構築するメリットやデメリットは以下の通りです。
- コストを抑えられる
- 時間や場所を問わずに利用できる
- データの共有や容量の拡張ができる
- 自社システムとの連携がうまくいかない場合がある
- 自社運用のオンプレミスと比べてカスタマイズ性が低い
クラウド環境下における情報システムの開発・運用管理などは、クラウドエンジニアが行います。
クラウドエンジニアが他のインフラエンジニアと違う点は、クラウドの特徴として仮想化技術や専門知識が必要になることでしょう。
インフラエンジニアの働き方

この項目では、インフラエンジニアの働き方について解説していきます。
保守運用の仕事は交代制で夜勤がある
インフラエンジニアの業務内容は幅広いですが、最初に配属されることが多いのが「保守運用」の仕事です。
保守運用の仕事内容は、主に以下のようなものとなります。
- システムが安定しているかの監視
- 環境改善の必要があるかの検証
- トラブル発生時の問題解決
常に何かしらの新しい仕事をするというよりは、トラブルが起きないか見張っておく業務になるため、交代制で夜勤も発生することが多いです。
夜勤も組み込まれると不規則な勤務になるため、それでも平気な人には向いている働き方でしょう。
なおクラウドエンジニアの場合は、自宅からインフラへアクセスできるので、Web系エンジニアのようなリモートワークが可能です。
インフラエンジニアの具体的なスケジュール
上流工程である設計を担当するのか、下流工程である保守運用を担当するのか、によってインフラエンジニアとしての働き方が変わります。
具体的なイメージを持ってもらうために、インフラエンジニアの1日を紹介します。
- 年中無休で稼働するネットワークの運用や保守作業をする
- 複数人で交代しながら働くため、残業は発生しづらい
- シフト以外の業務は時間外勤務として別途手当が支給
- クライアントの要望に合ったインフラ設計を行う
- 定時で帰れることが多い
- 企業により柔軟な勤務形態を採用している場合もある
上流工程と下流工程で多少働き方の違いがありますが、エンジニアとして残業が少ないというイメージです。
ただし、いざトラブルが発生してしまった時には、問題が解決するまで帰れないということもあります。
インフラエンジニアがキャリアアップするために必要な4つのスキル
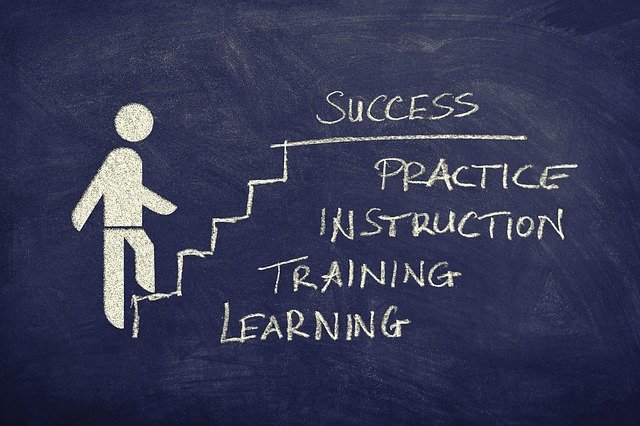
普及しているクラウドの知識から、情報セキュリティに関する技術まで幅広い知識が求められるでしょう。
具体的には以下の通りです。
- クラウドサービスの活用スキル
- 仮想化技術
- 情報セキュリティに関する技術
- マネジメントスキル
クラウドサービスの活用スキル
クラウドサービスに対応できるスキルがあると、インフラエンジニアとしての人材価値が高まります。
そのため、以下の各種クラウドサービスの利用経験があるとよいでしょう。
- AWS(Amazon)
- GCP(Google)
- Azure(Microsoft)
目安としては、各種クラウドサービスのメリットやデメリットの比較ができるレベルを目指してください。
仮想化技術
クラウドサービスを使うには、仮想化技術が必要になります。
仮想化とは、サーバーなどの物理的な制限にとらわれずに、ソフトウェアを統合・分割できるようにする技術のことです。
アプリケーションごとにサーバーが必要な状態から、1台のサーバー上に集約させて複数環境を稼働させることができます。
- VMWare
- Virtual Box
- Docker
インフラ関係で注目されているDockerなどのコンテナ型仮想化の技術があれば、より簡単に環境構築ができてスピーディに開発することができます。
情報セキュリティに関する技術
ITインフラの設計では、情報セキュリティに関する知識も求められています。
なぜならば、IT技術が進歩するほどサイバー攻撃などの危険性も高まってしまうからです。
例えばクラウドサービスを利用するケースでは、基本的にサービス提供側の企業がセキュリティ対策を取っています。
しかし、任せきりではなく利用者側の企業でも「このセキュリティ対策の基準で大丈夫かどうか」を判断する必要も出てくるのです。
インフラだけでなく、セキュリティに関して精通している人材はさらに必要とされるでしょう。
マネジメントスキル
インフラエンジニアとして開発するスキルに加えて、事業やプロジェクトのマネジメントスキルを身につけておくといいでしょう。
開発現場で使えるスキルとかけ合わせれば、現場以外でも広く活躍できるエンジニアになれます。
具体的には、以下のようなスキルを身につけておくといいです。
- コミュニケーション力
- メンバーを管理する能力
- 提案力
市場価値の高いエンジニアを目指している方は、既存のスキルとマネジメントスキルをかけ合わせられるように取り組んでみましょう。
インフラエンジニアのキャリアパス

ざっと挙げると以下のキャリアパスがあります。
- プロジェクトマネージャー(PM)
- スペシャリスト
- ITコンサルタント
- アーキテクト
プロジェクトマネージャー(PM)
開発メンバーとして現場に立つのではなく、プロジェクト全体の管理職としてプロジェクトマネージャーになる道もあります。
上流工程の案件もある企業に勤めてるエンジニアであれば、経験を積んで2~3年後にはPMになって活躍する人もいるでしょう。
- プロジェクト全体を管理する能力
- メンバーと信頼関係を築きチームを管理する能力
- ITに対する広い知識や実務経験
自分1人だけでなくチームをまとめる能力が必要なため、責任感は大きいですがやりがいもある仕事となっています。
スペシャリスト
スペシャリストとは、1つの専門分野を突き詰めた人材のことです。
そのためプロジェクトマネージャーと違い、技術力に特化する必要が出てくるでしょう。
インフラエンジニアの場合ですと、一般的に求められる仮想化技術よりもさらに最先端の技術が必要になってきます。
したがって、技術を磨きながら最新のトレンドに関する情報収集なども怠らないようにしなければなりません。
ITコンサルタント
ITについて企業が抱えている問題を解決するための提案をするコンサルタントも、インフラエンジニアのキャリアパスの1つになるでしょう。
インフラに問題があることで、効率の悪い運用になってしまっているケースもあるからです。
そのためには、以下のような準備をしておく必要があります。
- IT関連の幅広い知識
- 経済情勢や経営などのビジネス面の知識
- 課題解決力や提案力
- 論理的説明力
顧客のニーズや課題に合わせて経営戦略をアドバイスするには、技術力だけでなく提案力などのコミュニケーションスキルも必須になります。
企業の経営陣に対して提案することもあるため、論理的に説明する能力も必要です。
アーキテクト
経営戦略をもとにインフラの設計・構築を行うアーキテクトは、インフラエンジニアと共通する部分もあり、キャリアチェンジしやすい職種と言われています。
- 企業の経営戦略に合わせたWebシステムの設計図を作る
- 運用しやすい最適なシステム基盤を設計する
- システム全体の方向性や仕組みから運用・保守要件まで提示する
IT化やDX化が進んでいますので、ITアーキテクトのように高度なスキルを持った人材がますます必要なってくるでしょう。
インフラエンジニアからWebエンジニアに転職するのはアリ?
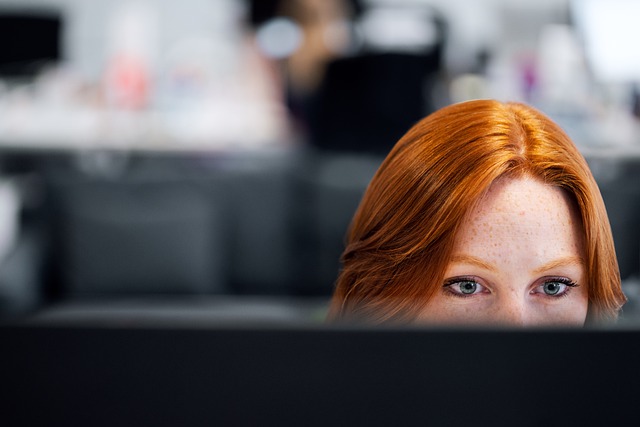
結論をお伝えすると、インフラエンジニアからWebエンジニアに転職するのはアリです。
なぜならば、Webエンジニアになればキャリアの幅も大きく広がるからです。
- ITアーキテクト
- ITスペシャリスト
- テックリード
- フルスタックエンジニア
- CTO
- フロントエンドエンジニア
- サーバサイドエンジニア
- プロジェクトマネージャー
- VPoE
- Webディレクター
このように、Web系の開発エンジニアになると幅広いキャリアパスを持つことができます。
もちろん、インフラエンジニアの仕事は安定しているので、長く働くことができます。
シフトも決まっているので、残業が少なくプライベートの時間も取れるでしょう。
しかしインフラエンジニアの場合ですと、昇級してもこなす仕事があまり変わらないということもあります。
そのため、将来的なキャリアの選択肢を広げたいのであれば、Webエンジニアへの転職を考えるのも一つの手でしょう。
なお、Webエンジニアへキャリアチェンジする際にも、インフラエンジニアとしての経験が無駄になることはありません。
- バックエンドエンジニアとの共通点が多く知識を応用できる
- ITインフラの技術とプログラミングを学べば希少価値の高い人材になる
- インフラの知識を持つフルスタックエンジニアになれる
このように、インフラエンジニアの経験がマイナスになることはありません。
インフラエンジニアは専門性が高いため、転職をしてWebエンジニアの知識と組み合わせると希少な人材になれるでしょう。
しかし、インフラエンジニアからWeb系の開発エンジニアへの転職は異業種への転職扱いになります。
私たちが運営しているプログラミングスクールRUNTEQでは、元インフラエンジニアの方がRuby on Railsでの開発を学習されて、Web系自社開発企業へ転職した方もいます。
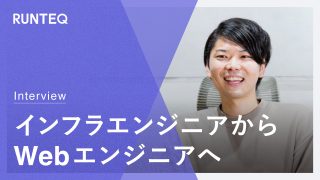
このように、インフラエンジニアからWeb系の開発エンジニアへ転職する場合は、未経験の方と同様に開発を学んでから転職する必要があります。
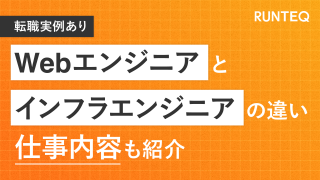
まとめ
今回の記事では、インフラエンジニアの将来性やキャリアパスまで幅広く解説しました。
インフラエンジニアの中には、交代制の夜勤業務を任されることもあるため、Web系エンジニアほどの人気はありません。
しかし、今後もインフラの需要は減らないことから、将来性としては問題ない職種でしょう。
また、インフラエンジニアの知識を活かしてWebエンジニアに転職すれば、スキルのかけ合わせにより市場価値の高いエンジニアになることも可能です。
- インフラエンジニアはシフトが決まっていて夜勤がある
- クラウド化により必要なスキルも変化するが需要はまだ減らない
- インフラエンジニアからWebエンジニアに転職することも可能
弊社では、開発現場が求めるエンジニアになるためのプログラミングスクール「RUNTEQ」を運営しております。
この記事を読んで、少しでもWebエンジニアに興味を持った方は、ぜひ無料の無料カウンセリングへ足を運んでください。