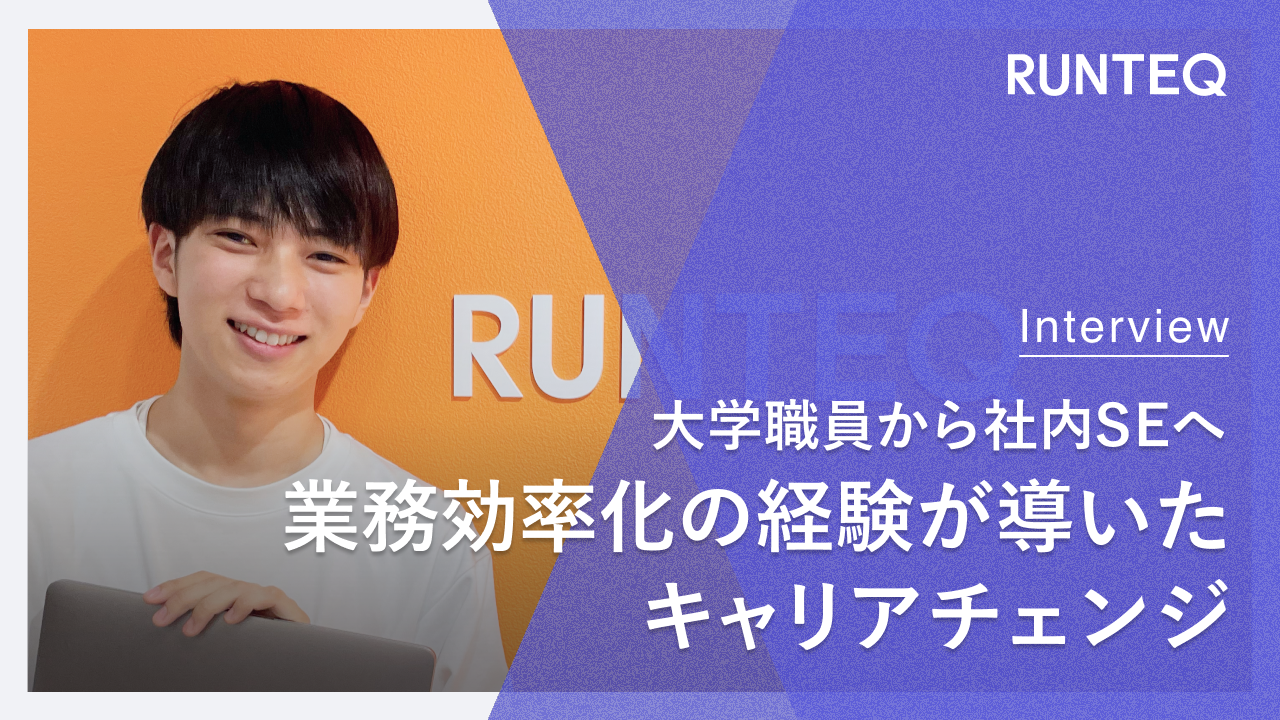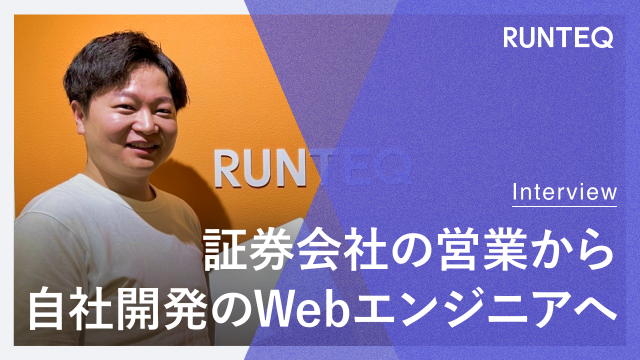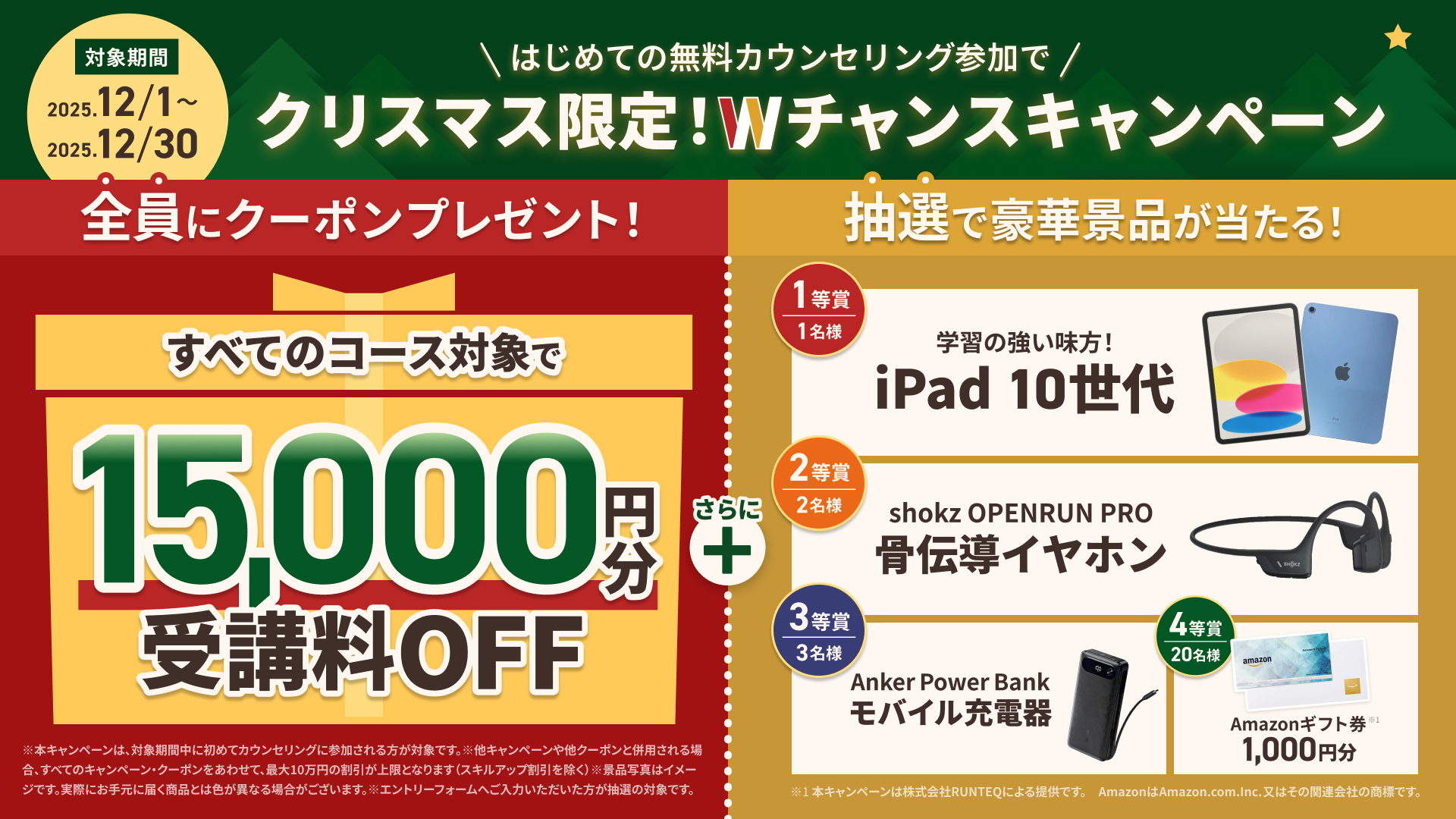大学職員から社内SEへとキャリアチェンジを果たした、しまたまさん。
「デジタル化を進めたい」という思いを胸にRUNTEQに入学し、学習期間中は100回を超えるイベントに参加するなど、仲間とともに切磋琢磨しながら学びを深めてきました。
未経験からプログラミングに挑戦したしまたまさんに、RUNTEQ(ランテック)での学びの過程や就職活動、そして現在のお仕事について伺いました。
【プログラミングスクールRUNTEQ卒業生インタビュー vol.90】
※RUNTEQ学習期間は2024年4月~2025年1月
業務改善に関心を持ち、異業種からキャリアチェンジへ
Q. これまでのご経歴と、プログラミングに興味を持ったきっかけを教えてください。
都内の私立大学に入学し、英文学科で英語を学びました。卒業後は、別の都内の私立大学で職員として勤務し、学生の就職支援業務に携わりました。
学生相談や海外インターンの手配、求人登録などを担当する中で、業務改善に関心を持ち、Google Apps Scriptを使った効率化などにも取り組みました。
その経験をきっかけにプログラミングに興味を持ち、いくつかのスクールを比較検討した上でRUNTEQ(ランテック)に入学。約半年の学習を経てエンジニア転職を目指し、学習に専念しました。
2025年5月に株式会社Kaienへ入社し、現在は社内SEとしてシステム開発や業務改善に携わっています。
▼しまたまさんがご入社された株式会社Kaien様の記事はこちら:

Q. 異業種からエンジニアを目指そうと決意した理由は何ですか?
前職で業務改善を進める中で、GoogleフォームをカスタマイズするためにGAS(Google Apps Script)を使ったことがきっかけでプログラミングに興味を持ちました。手作業で行っていた業務を自動化できたことで「これは面白い」と感じたのが最初の一歩です。
もともとパソコンには親しみがあり、母がパソコン教室の先生だったこともあって、子どもの頃から動画編集や友達と映画を作って公開するなど、自然とパソコンに触れてきました。そうした経験から「自分はパソコンを使う仕事に向いているのでは」と思うようになり、その延長でエンジニアという職業に興味を持つようになりました。
また、周囲にエンジニアがいたことも後押しになりました。友人の中に数人エンジニアがいて、「柔軟に働けて自分に合っている仕事だ」と楽しそうに話しているのを聞き、自分もその働き方に惹かれました。
エンジニア転職を意識し始めてから行動に移すまでは早く、興味を持ってから間もなくスクールへの入学を決めました。
Q. 数あるスクールの中で「RUNTEQ」を選んだ理由は何ですか?
「学習1,000時間」の厳しさが魅力でした。
仮に300時間程度の学習で転職して合わなかった場合より、1,000時間取り組んでからの結果なら納得できる、と考えました。大変な道を選び、その成果に期待したいという気持ちでしたね。
RUNTEQは基礎に加え、要件整理や設計、アプリ開発まで自力で行う応用的な時間が含まれると聞き、納得感がありました。
また、サポート体制の手厚さも決め手のひとつでした。
オンラインで学ぶとなると、わからないことがあった時に一人で詰まってしまう不安がありましたが、RUNTEQでは毎日1回技術面談を利用できるほか、コミュニティで同期と教え合える環境が整っていると知り、「これなら続けられそう」と思えました。
以前、学生のサポートをしていた経験からも「相談しやすい環境の大切さ」は強く感じていたので、RUNTEQにはそれがあるという確信が持てたことも大きかったです。
Q. スクールで学んだことが、実際の仕事で役に立つか不安に感じることはありましたか?
学んだことが仕事で活かせるかという不安はあまりありませんでした。それよりも「新しい世界を見てみたい」という気持ちのほうが強かったと思います。
前職では、紙を使った業務や人の手に頼る作業が多く、効率化の余地を感じる場面がよくありました。そうした環境の中で、もっと仕組みづくりや改善に関わる働き方がしたいと感じたのが、エンジニアを目指す大きなきっかけになりました。
教育業界という性質上、伝統的なやり方が残るのは自然なことですが、自分自身はより柔軟で合理的な考え方を活かせる仕事に挑戦したいと思うようになりました。前職での経験があったからこそ、自分がどんな働き方をしたいのか、何にやりがいを感じるのかを明確にできたと感じています。

1,000時間をやり抜くための工夫と習慣づくり
Q. 1000時間という学習時間をどのように確保しましたか?
最初は仕事をしながら学習を進めていて、平日は1日3時間ほど勉強していました。残業が少なかったので、通勤時間や移動中の電車の中でもパソコンを開いて学習していました。
フェスに行くときもノートPCを持って行き、行き帰りの電車でコードを書いていたくらいです。(笑)
学ぶこと自体が好きなので、勉強時間を確保するのは苦ではありませんでした。
退職してからは学習時間が大幅に増え、多い日は9時間ほど取り組むこともありました。もともと学習習慣があり、前職のときもTOEICの勉強などを自主的に続けていたので、「英語の勉強がプログラミングに変わっただけ」という感覚でした。英語のドキュメントにも抵抗がなく、スムーズに理解できたのも助けになりました。
学習期間を通して「辛い」と感じることはほとんどなく、自然と日常の一部として学びを続けられていたと思います。ただ、フルコミットしてからは生活リズムが崩れないように意識していて、毎朝8時半には起きて、RUNTEQの受講生たちが自主的にオンラインで開催している、ラジオ体操に参加するなど、規則正しい生活を心がけていました。
そうした習慣づくりが、長期間の学習を続ける上で大きな支えになりました。
Q. 学習期間中で一番印象的に残っていることは何ですか?
受講期間中で一番印象に残っているのは、同期会のために大阪まで行ったことです。卒業祝いを兼ねてRUNTEQ生で集まろうという話になり、開催場所が大阪に決まったんです。
そのためだけに新幹線のチケットを取り、カプセルホテルに泊まって、一日中同期のメンバーと過ごしました。朝早くに出発してご飯を食べ、たこ焼きパーティーやカラオケにも参加して、とても充実した一日でした。
20人ほど集まった会で直接顔を合わせて話すことで、オンラインでは得られない刺激を受けました。東京近郊では近くに住む受講生同士で集まって勉強会を開くこともあり、その流れでチーム開発の発足に繋がったこともあります。
仲間とのつながりが大きなモチベーションになり、学習の時間がより楽しく、意味のあるものになったと感じています。
Q. イベントに100回以上も参加されていたそうですね!参加のきっかけを教えてください。
イベント参加のきっかけは、入学してすぐに参加した懇親会でした。入学から1週間ほどのタイミングで思い切って参加してみたところ、同じ期の方がもう一人いて、その出会いが大きなきっかけになりました。
その時にコミュニティの雰囲気を感じられたことで、イベント参加のハードルが一気に下がったのを覚えています。
それ以来、自然とイベントに参加するようになり、気づけば100回以上に達していました。仕事をしながらの時期もほぼ毎日のように何かしらのイベントに参加していて、コミュニティの活発さや仲間とのつながりが、学習を継続する大きな原動力になっていました。
Q. 学習を続ける中で、モチベーションが下がったり不安になった時期はありましたか?
エンジニアになりたいという気持ちが揺らいだ時期はありました。特に就職活動のときはそれを強く感じました。
受講期間中は、プロダクトを作ること自体が純粋に楽しくて、「こういう機能を実装できた」「できなかったことができるようになった」という達成感がモチベーションになっていました。ただ、就活が始まると「なぜエンジニアになりたいのか」と問われる場面が増え、明確に言葉にできず悩むことがありました。
そんなときに思い出したのが、RUNTEQに入ったときの原点でした。前職で感じていた「業務効率化への興味や、アナログな仕事をデジタルの力で解決する面白さ。」を思い出したことで、「自分はこういう課題を解決したくてエンジニアを目指したんだ」と再確認できました。
そこからは、そうした思いを軸に会社探しを進められるようになり、就活でも自然に言葉にできるようになりました。初心を思い出せたことが、自分にとって大きな転機だったと思います。
個人開発とチーム開発で得られたそれぞれの学び
Q. 卒業制作(Webアプリ制作)では、どのようなアプリを作成されましたか?また、作成で意識した部分はどこですか?
個人開発では、「PEOPLE 1」というバンドの非公式ファンサイトを制作しました。PEOPLE 1のリスナー同士が情報を共有し合い、バンドの魅力をより深く知ってもらうことを目的にしたWebアプリです。
現在はサービスを停止していますが、公開していた当時は多くの方に見てもらうことができ、総PV数はおよそ1万2,000回に達しました。ファンの方から「使いやすかった」「こういうサイトを待っていた」といった反応をもらえたのが本当に嬉しかったです。
PEOPLE 1のファンの中にはエンジニアの方もいて、「この技術を使っているんですね」とDMをいただくこともありました。好きなものをきっかけにして、同じ興味を持つ人とつながれたのはとても印象的な経験でした。
また、チーム開発にもチャレンジしました。最初は大変でしたが、開発を通じてプルリクエストの書き方やチームでのやり取りなど、実務に近いスキルを身につけることができました。その経験は就職活動でも自信を持って話せるエピソードとなり、とても良い学びになったと感じています。
▼しまたまさんが作成されたWebアプリ▼
「ぴぽの掲示板 」
PEOPLE 1の非公式ファンサイトです。PEOPLE 1リスナーが情報を共有し合い、PEOPLE 1をより深く知ってもらうことを目的としています。
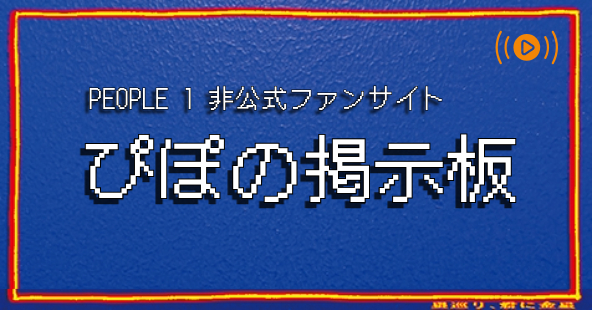
Q. 個人開発とチーム開発は違う大変さと楽しさがあると思いますが、それぞれいかがでしたか?
個人開発では、自分が「これがいい」と思ったものをとことん突き詰めて形にできるのが一番の魅力でした。UIやデザインの細かい部分を工夫したり、技術的にこだわりたいところをすぐ反映できたりと、思いついたアイデアを自由に試せるのが楽しかったです。
一方でチーム開発は、メンバーそれぞれの得意分野を活かして一つのプロダクトを作り上げていく面白さがありました。自分は当時バックエンドに興味があったのですが、フロントエンドが得意なメンバーがとても魅力的な画面を作ってくれたりして、その技術力に刺激を受けることも多かったです。
お互いの強みを尊重しながら協力する中で、ひとりでは得られない学びがたくさんありました。
また、チーム開発を通してGitFlowでのブランチ運用やコンフリクト対応なども経験できたのは大きかったです。実際に現職で「GitHubの理解があるね」と言ってもらえたことがあり、RUNTEQでの開発経験が実務に直結していると感じました。
“デジタル化を進めたい”想いを形にした就職活動
Q. 就職活動は、どのように進めましたか?
就職活動はおよそ2か月ほど取り組みました。
最初のうちはなかなか面接が通らず、10社以上受けても結果が出ない時期が続きました。最終面接まで進めたのは3社ほどだったと思います。
Q. 転職活動で苦戦したことはありますか?
転職活動で一番苦戦したのは技術面接でした。当時は知識もまだ浅くて、「これはどうしてこう動くの?」と聞かれても、うまく説明できないことが多かったです。
RUNTEQの講師に面接対策をしてもらったときには、具体的で的確なフィードバックをいただき、とても勉強になりました。それでも実際の面接では、想定と違う質問を受けたり、思わぬ部分を深掘りされたりして苦戦しましたね。
受講当時は「とにかく動けばいい」という意識でコードを書いていた部分もあって、面接で「なぜその実装方法を選んだのか」と聞かれると答えに詰まることがありました。今振り返ると、動かすことだけでなく「なぜそう動くのか」「どう考えてそう設計したのか」を意識して学んでおけばよかったなと思います。
この経験が、今後エンジニアとしてより深く考えながら開発する意識につながっています。
Q. RUNTEQの就職サポートはいかがでしたか?
就職活動の中で、キャリアアドバイザー(CA)さんの存在はとても大きかったです。
CAさんに面談していただき、さまざまな角度からアドバイスをもらいました。「こういう伝え方の方が良いかもしれません」「この経験をもう少し掘り下げてみましょう」といった具体的な提案をたくさんいただき、本当に心強かったです。
また、同期とも頻繁に情報交換をしていました。面接対策のコツを共有したり、「この学習をやってみたら効果があった」といった体験を話し合ったりして、互いに励まし合いながら進めていました。
そうしたサポートや仲間とのつながりがあったおかげで、少しずつ面接も上手くいくようになりました。
Q. 就職活動で、ご自身が評価されたと感じる点はどこですか?
印象に残っているのは、前職での業務改善の経験です。アナログな業務フローに効率面での課題を感じ、GAS(Google Apps Script)を用いて自動化を提案・実装しました。
結果として、学生にも職員にも利便性の高い仕組みを構築することができ、上司からも高く評価されました。
業務時間をどの程度削減できたかなど、具体的な成果を数値で説明したことで、面接でも説得力をもって伝えられたと思います。
Q. 内定承諾の決め手は何でしたか?
内定を承諾した決め手は大きく2つありました。
ひとつは、前職で携わっていた就職支援の仕事と、Kaienが行っている障害者の就労支援事業に共通点があったことです。自分がこれまで関わってきた分野とつながりがあると感じ、これまでの経験も活かしながら新しい挑戦ができると思いました。
もうひとつは、面接でお会いしたエンジニアの方々の印象がとても良かったことです。技術的な知識だけでなく、話し方や考え方に誠実さを感じて、「この人たちのもとでなら安心して働ける」と思えたのが大きな決め手でした。

仕事に活きる、RUNTEQで身につけたマインド
Q. 現在の担当業務と1日の流れについて教えてください。
現在は、社内SEとしてシステム開発や業務改善に携わっています。
1日の流れは、朝8時頃に起きて朝食をとり、9時から仕事を始めます。まずはその日のタスクを整理したり、Slackやメールを確認したりしてから作業に入ります。朝会でチーム全体で進捗共有や課題の確認を行った後は、基本的に自分の作業やミーティングに集中して取り組みます。昼休憩を挟み、18時に業務が終了します。
会社の方針として残業がほとんどなく、基本的に定時で仕事を終えられるのもありがたいですね。
また、働き方にもとても満足しています。現在はほぼリモートワークで、週4日が在宅勤務、週1日が出社です。趣味の時間をしっかり確保できるため、仕事とプライベートのバランスがとりやすく、自分に合ったリズムで働けていると感じています。
Q. 元々抱いていた「デジタル化を進めたい」という思いは実現しましたか?
入社後は、「デジタル化を進めたい」という自分の目標をしっかりと実現できていると感じます。現在の会社では全国に事業所を展開しており、新しい拠点が増えるたびに人の手で行われていた作業を、仕組み化によって効率化する取り組みを進めています。
上司とも「手作業を減らし、仕組みで解決していこう」という考え方を共有できており、まさに自分が目指していた形で仕事ができています。日々の業務の中で、デジタルの力で課題を解決していく面白さを実感しています。
Q. チームの雰囲気や職場環境はいかがですか?
提案がとてもしやすい環境です。基本的に全員リモートワークですが、毎朝オンラインで集まって顔を合わせる時間があります。
その場で、各事業所で起きたヒヤリハットやちょっとした課題を共有し、システムチームとして「こうすれば解決できるかも」「ここを改善したら同じミスが起きにくいかも」といった意見交換をしています。
そうしたミーティングでは、メンバー全員が積極的に意見を出しており、経験の浅い自分でも気軽に提案できる雰囲気があります。入社して間もない頃から発言しやすいと感じていて、「若手の意見もきちんと受け止めてくれる環境」だと思います。
リモートワークだとコミュニケーション面が心配になることもあるかもしれませんが、システムチームでは「50点くらいの段階でも一度相談してみる」という方針があります。完璧に整理できていなくても気軽に上司やメンバーに相談できる雰囲気があり、働きづらさを感じることはありません。
Q. 仕事でギャップを感じることはありますか?
想定外だったのは、思っていた以上にコミュニケーションの機会が多いことでした。
特に自分の会社では、事業部の方から話を聞いて課題を整理し、「こういう仕様にしてみてはどうですか?」と提案するところから始まります。その後もチーム内で仕様を詰めたり、実装方針を話し合ったりと、どの工程でも密にコミュニケーションを取る必要があります。
入社前は、エンジニアは一人で黙々とコードを書いている時間が多いイメージを持っていたのですが、実際はチームや他部署との連携が欠かせません。人と話しながら一緒に課題を解決していく仕事なんだと改めて感じました。
Q. 仕事で役立っているRUNTEQでの学びはありますか?
RUNTEQで学んで良かったと感じることのひとつに、「相談する相手の時間も使っている」という意識を持てるようになったことがあります。
今の職場では上司の方々がとても忙しいので、相談する前に自分の中で「何が分かっていないのか」「どこまで調べたのか」を整理してから話すようにしています。そのおかげで、質問の仕方が明確になり、相手にとっても伝わりやすくなったと思います。実際に上司から「質問の仕方がうまいね」と言ってもらえたこともあり、RUNTEQで身につけたマインドが今の仕事に大きく活きています。
また、テキストでのコミュニケーションでも同じ意識を持つようにしています。エンジニア以外の人にも伝わるように工夫したメッセージが評価されることもあり、相手の立場を考えて情報を整理して伝える力が自然と身についたと感じます。
RUNTEQでの学びを通じて、「どう伝えるか」を意識できるようになったのは大きな財産です。
これからエンジニアを目指す方へ/今後の目標
Q. 未経験からエンジニアになってみて、どんな人がエンジニアに向いていると思いますか?
自分の感覚で言うと、「自分が作ったものを誰かに喜んでもらえることが嬉しい」と思える人は、エンジニアに向いていると思います。
技術的な知識やスキルももちろん大切ですが、それ以上に「人の役に立ちたい」「自分の作ったもので誰かを助けたい」という気持ちが原動力になると、辛い時期も乗り越えられる気がします。
自分も実際に、社内で自分が作った仕組みが喜ばれたり、「使いやすくなった」と言ってもらえたりすることが大きなモチベーションになっています。技術の分野が違っても、その“誰かのために作る楽しさ”を感じられる人は、きっとエンジニアという仕事に向いていると思います。
Q. これからエンジニア転職に挑戦したいと考えている方へ、やっておくといいことはありますか?
これからエンジニア転職やプログラミングの勉強を始めようとしている方に伝えたいのは、「現職で頑張った経験を作っておくこと」です。
たとえエンジニア職でなくても、「これを改善した」「この仕事に力を入れた」というエピソードがあると、転職活動でも大きな武器になります。その経験の中で感じた楽しさや工夫した点は、エンジニアになってからの課題解決や提案にもきっと生きてくると思います。
プログラミングの勉強については、「なぜこの書き方をしたのか」「なぜこの機能を作ろうと思ったのか」という意識を持って進めるのがおすすめです。単に動かすことをゴールにせず、考え方の背景まで理解しようとすることで、より深い学びになりますし、将来の面接や実務でもしっかり自分の言葉で説明できるようになると思います。
Q. 今後の目標はありますか?
今後の目標は、AI時代にしっかりついていけるエンジニアになることです。
今やAIを使わない手はないと思っていますし、社内でもAIを積極的に活用していく流れがあります。その中で「AIをどう使えば一番効率的に問題を解決できるか」を考え、実際に活かせるエンジニアになりたいと考えています。
そのためにはまず、自分自身が今扱っている技術の基礎をより深く理解し、応用的な知識も磨いていく必要があると感じています。AIを活用すると、動くコードはすぐに作れるようになりますが、構造的に無理のあるコードや、後々修正が難しくなるような実装も増えていきます。だからこそ、アーキテクチャの考え方や設計の原則を理解し、AIに依存しすぎずに最適な形を導けるようになりたいです。
また、自分はどちらかというと「1から10を磨く」のが得意なタイプですが、チームには「0から新しい仕組みを生み出す」ことが得意な人もいます。そうしたメンバーから学びながら、自分もアイデアを形にできる力を身につけて、0から10まで対応できるエンジニアを目指したいです。
編集後記
いかがでしたでしょうか?
「現状を変えたい」という思いを行動に移し、努力を積み重ねながらエンジニアとして新しいキャリアを切り開いていった過程が伝わってきました。
RUNTEQは、しまたまさんのようにさまざまなバックグラウンドを持つ方々が本気でエンジニアを目指せる環境を提供しています。
単にスキルを教えるだけでなく、学習の進め方、モチベーションの保ち方、そして転職活動まで、一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。
RUNTEQに興味を持たれた方は、ぜひ一度、無料キャリアカウンセリングにお越しください。あなたの可能性を、私たちと一緒に広げてみませんか?
ご予約はこちらから可能です。ぜひお待ちしております。
https://runteq.jp/