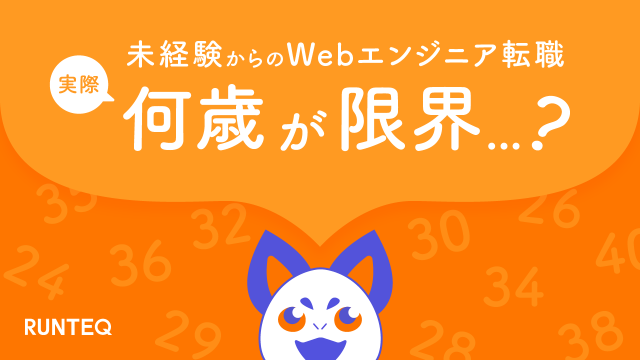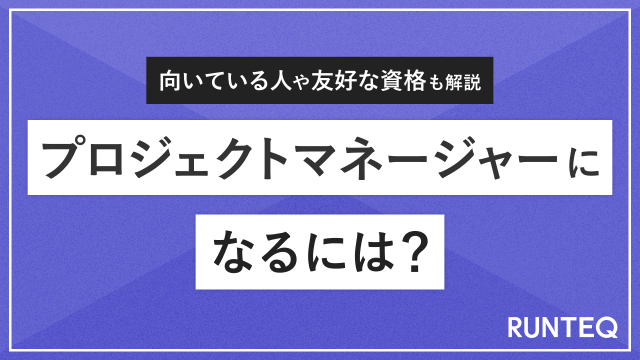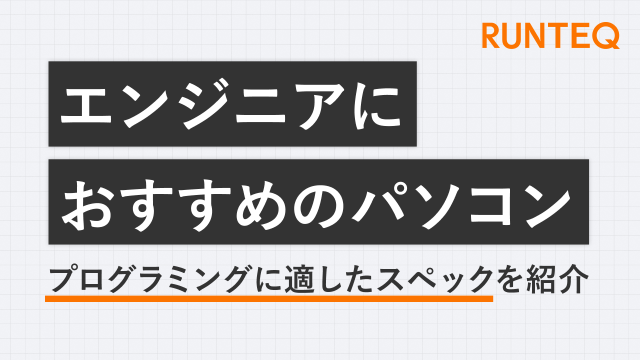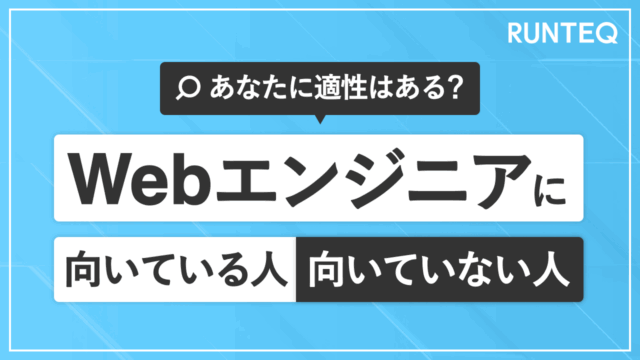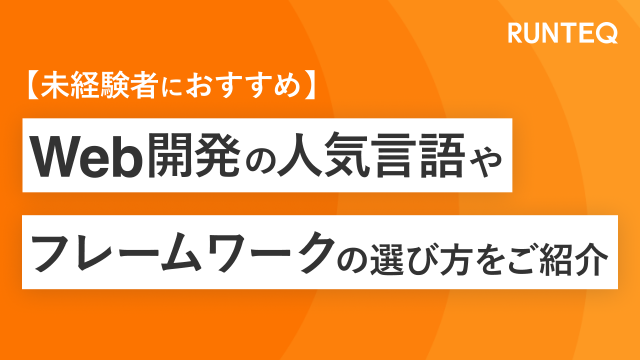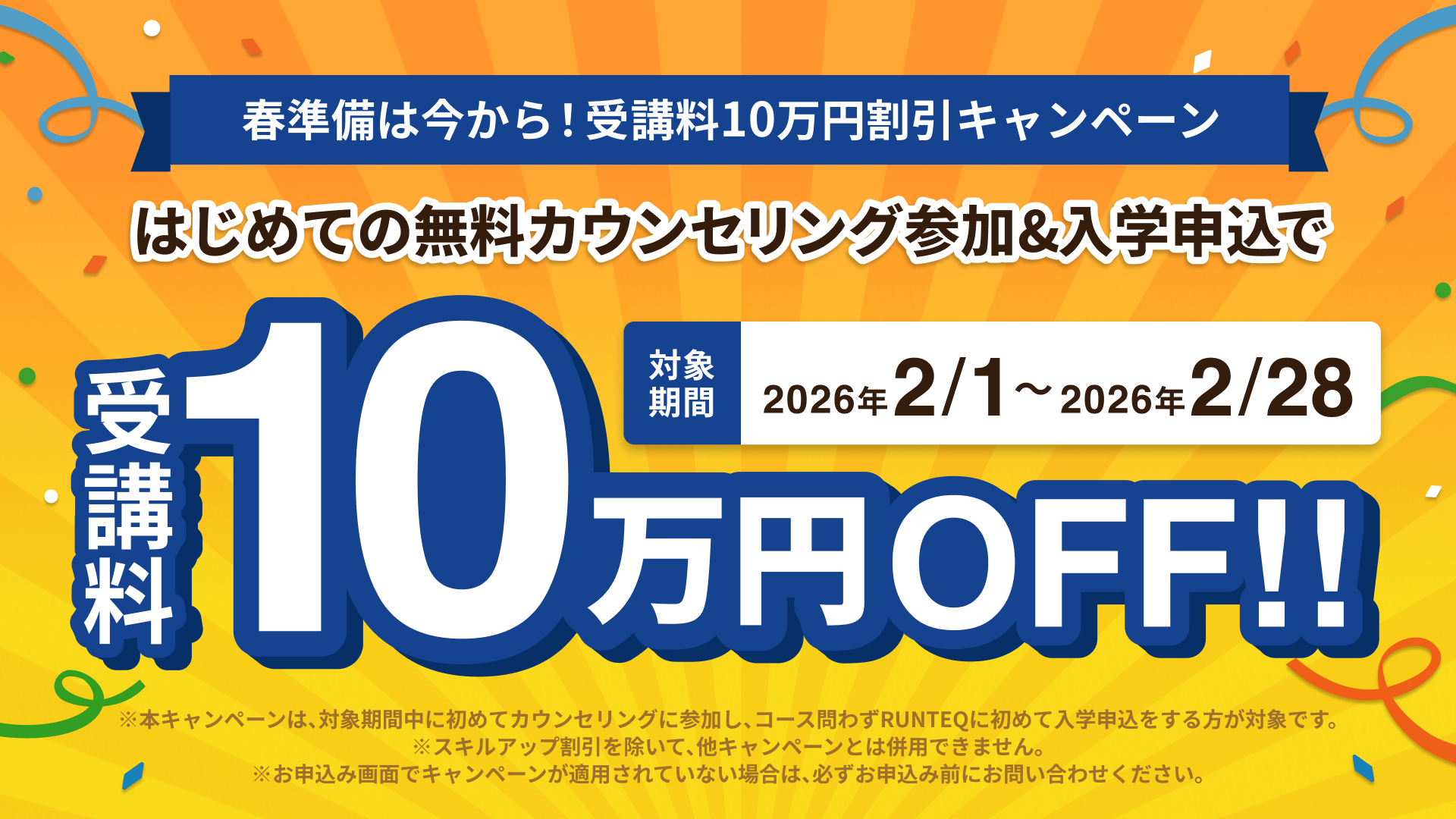【Web系エンジニアを目指す大学生向け】就職を成功させるための完全ガイド
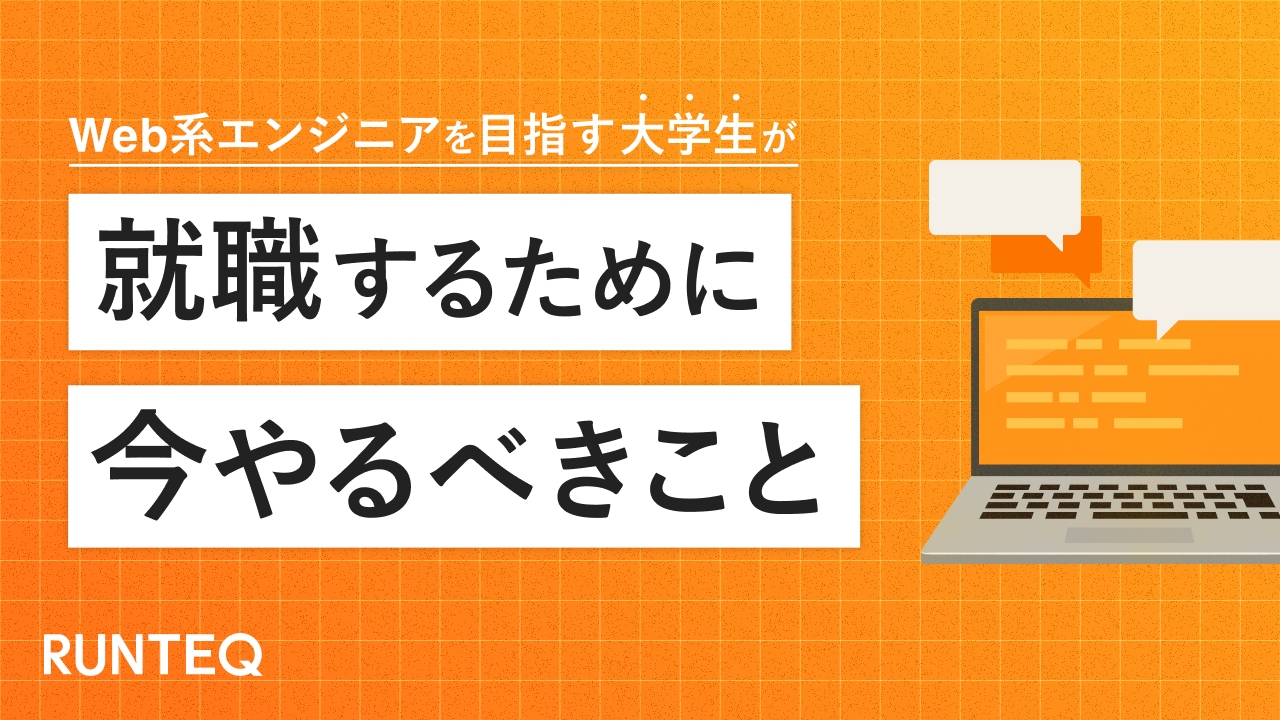
IT業界の急速な成長に伴い、Web系エンジニアの需要は高まる一方です。将来性豊かなこの分野で活躍したいと考える大学生も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- Web系エンジニアとして就職を目指す大学生は、具体的に何をすべきなのか?
- 大学生のうちに身に付けておくべきスキルは何か?
- そもそもWeb系エンジニアとは何なのか? そのメリットとは?
といった疑問を解消していきます。
「大学生活を活かしてWebエンジニアとしてのキャリアをスタートさせたい!」「新卒で希望の企業に入るための具体的な方法が知りたい!」
そんなあなたは、ぜひ最後まで読んで、未来への一歩を踏み出す準備を始めましょう!
\ あなたに合った学習法を相談! /
無料で話を聞いてみる ▶︎▶︎
そもそもWeb系エンジニアとは?

Web系エンジニアとは、私たちが日常的に利用するWebサイトやWebアプリケーション(ECサイト、SNS、動画配信サービスなど)の設計、開発、運用、保守を専門に行う技術者のことです。彼らの仕事は、インターネットを通じた様々なサービスを支える、まさに現代社会に不可欠な存在と言えるでしょう。
Web系エンジニアは、担当する領域によって大きく以下の2つに分けられます。それぞれの特徴と魅力を理解し、自分がどちらの分野に興味があるか考えてみましょう。
バックエンドエンジニア
バックエンドエンジニアは、ユーザーの目には直接触れないサーバーサイドの処理やデータベースの構築、システム連携などを担当します。
Webサービスがスムーズかつ安定して動作するための基盤を作り上げる、まさに「縁の下の力持ち」です。サーバーサイドエンジニアとも呼ばれます。
主な使用言語は「Ruby」・「PHP」・「Python」などです。
- Webサービスの根幹を支える重要な役割を担う。
- 論理的な思考力や問題解決能力が特に求められる。
- 求人数も多く、特にRuby on Railsは未経験者にも学びやすく案件も豊富。
フロントエンドエンジニア
フロントエンドエンジニアは、ユーザーがWebサイトやアプリケーションを操作する際に直接目にする部分(ユーザーインターフェース)の設計・構築を行います。デザイン性と機能性を両立させ、快適なユーザー体験(UX)を創り出すことが求められます。
一昔前まではフロントエンドエンジニアという職種は存在せず、「マークアップエンジニア」や「Webデザイナー」がフロントエンドを担当していました。
しかし技術革新が進むにつれ、より高いスキルが求められる作業が増えたため、フロントエンドエンジニアという職種が生まれました。
主な使用言語: HTML、CSS、JavaScript、およびJavaScriptのフレームワーク(React、Vue.js、Angularなど)
- ユーザーがWebサイトやアプリケーションを操作する際に直接目にする部分の設計・構築を担当。
- Web技術の高度化に伴い、より専門的なスキルが求められるようになった。
Web系エンジニアとして就職するメリット
メリットはいくつもありますが、代表的なものは以下の2つでしょう。
■今後も発展していく可能性が高い業界である
■努力次第で高収入が見込める
「どんなに頑張っても収入が上がらない」という職種もたくさん存在しますが、ITエンジニアの場合、努力次第でどんどん自分の収入を上げることが可能です。
IT業界は実力主義なので、スキルを高めて大きな成果を残せば、給料も上がりやすいです。
特にWeb系は、IT業界の中でも規模が大きく、現在も成長中の業界。
アメリカの5大IT企業GAFAM(Google・Amazon・Facebook・Apple・Microsoft)のほとんどがWeb系サービスをメインとした会社であることも、ITの中でWeb系が強いということを顕著に表しています。
技術革新は日進月歩で進んでいるため、Webエンジニアは、まだまだ若く吸収力が高い大学生にとっては最適な職種でしょう。
大学生がWeb系エンジニアを目指す5つのメリット
Web系エンジニアは、大学生の皆さんにとって非常に魅力的なキャリアパスです。その主なメリットを5つご紹介します。
高い将来性と市場価値
IT業界、特にWeb業界は技術革新が著しく、常に新しいサービスや技術が生まれています。スマートフォンの普及やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、Web系エンジニアの需要はますます増加しており、その市場価値は非常に高いと言えます。
経済産業省の調査でもIT人材の不足が指摘されており、スキルを身につければ将来にわたって活躍できる可能性が高いでしょう。
実力主義の世界で高収入を目指せる
IT業界は比較的実力主義の傾向が強く、年齢や学歴よりもスキルや実績が重視されます。スキルを磨き、価値ある成果を生み出すことで、若いうちからでも高い収入を得ることが可能です。
「頑張っても給料が上がらない」といった悩みとは無縁で、自身の努力次第でキャリアアップと収入アップを実現しやすい環境です。
場所や時間に縛られない柔軟な働き方も可能
Web系エンジニアの仕事は、PCとインターネット環境があれば場所を選ばずにできることが多いため、リモートワークやフレックスタイム制を導入している企業が増えています。
これにより、通勤時間の削減や、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が実現しやすくなります。
知的好奇心を満たしながら成長できる
Web業界は技術の進化が非常に速く、常に新しい技術やトレンドが登場します。AI、クラウド、ビッグデータ、IoTなど、最先端技術に触れる機会が多く、知的好奇心を満たしながら自己成長を続けられる刺激的な環境です。変化を楽しみ、学び続ける意欲のある人にとっては最適な職種と言えるでしょう。
若いうちから大きな裁量を持って活躍できるチャンス
特にスタートアップやベンチャー企業では、年齢に関わらず意欲と能力のある人材に大きな裁量権が与えられることがあります。
自ら手を挙げて新しいプロジェクトに挑戦したり、サービスの開発に深く関わったりと、若いうちから責任ある仕事に携わり、大きな達成感を得られるチャンスが豊富にあります。
【厳選】Web系エンジニアを目指す大学生がやるべきこと6選
では、Web系エンジニアになるために、大学生のうちに具体的に何をすべきなのでしょうか?ここでは6つの重要なポイントを解説します。
①インターンに参加する
インターンとは、大学在学中に会社で実際に働いてみる職業体験のことです。
未経験の状態でもインターンに参加することができ、会社の人が実務を教えてくれるため、非常に貴重な経験ができます。
エンジニア関連のインターンは、一日から一週間程度で終了する短期間のものから、半年以上継続できる長期のものまで色々あるので、本気でエンジニアになりたいのならば、一度は参加して現場の雰囲気や実務の内容を把握しておくべきでしょう。
インターンへ参加するのは早ければ早いほど良いので、可能ならば大学1~2年生のうちに積極的にインターンへ申し込んでみてください。
短期間のインターンの場合は、企業説明や業務のさわり程度を教わって終わりになってしまうため、できれば中長期で参加した方がよいです。
スタートアップ系の企業は長期でのインターンを歓迎しているところも多いので、そういった企業を中心に探してみてください。
②エンジニアとしての基礎知識を身に付けておく
Web業界は常に人手不足であり、入社後に手厚い研修が受けられるとは限りません。そのため、大学生のうちにITに関する基本的な知識を身につけておくことが重要です。
従って、大学生のうちに「最低限のITスキル」を身に付けておく必要があります。
就職前に、実務レベルのスキルや専門的な知識まで身に付けるのは難しいですが、せめて基本的な知識だけは身に付けておきましょう。
具体的な方法としては、「基本情報技術者試験」や「Ruby技術者認定試験」といった資格を取るのがおすすめです。
資格を取得するための勉強過程で自然と知識が身に付く上、資格を保有しているということで会社からも一定の評価を得られるため、一石二鳥です。
③プログラミングスキルを習得する
Webエンジニアを目指すなら、プログラミングスキルは必須です。特にバックエンドを目指すならRubyやPHP、フロントエンドならJavaScriptの学習から始めると良いでしょう。
その際、独学で進めるのはあまり推奨できません。
間違った勉強の仕方をしてしまうと効率が悪いですし、壁にぶつかった時に一人で乗り越えるのはかなり難しいです。
よって、本気でWebエンジニアになりたい場合は、大学在学中にプログラミングスクールに通うのがおすすめです。
大学と並行して通うことができるカリキュラムを用意しているプログラミングスクールも多く存在します。
お金はかかってしまいますが、自分の将来への投資だと考えると決して無駄なお金ではないでしょう。
④文章力を磨く
エンジニアの仕事は、黙々とコードを書くだけだと思っていませんか?
実は、それは大きな誤解です。実際の開発現場では、「文章によるコミュニケーション能力」がプロジェクトの成否や個人の評価を大きく左右します。
エンジニアにとって「伝わる文章力」は、コードを書くスキルと同様に重要です。 設計書の作成、チーム内での情報共有、顧客への説明など、多くの場面で正確かつ分かりやすい文章が求められ、プロジェクトの成否や個人の評価にも影響します。
最近はLINEやチャットなど短文でのコミュニケーションが主流ですが、エンジニアには「相手に正確に意図が伝わる、論理的で構造化された文章」を書く能力が不可欠です。
この文章力を鍛える効果的な方法の一つが、学習記録や技術解説など、特定のテーマを持ったブログを定期的に書くことです。これにより、要点を整理し、分かりやすく伝える訓練になります。
ブログを書き続けることは、文章力を向上させるだけでなく、就職活動の際には自身のスキルアップの過程を示すポートフォリオとしても活用でき、企業からの評価につながる可能性も秘めています。
⑤自己解決力を育てる
エンジニアとして活躍し続けるためには、技術力と同じくらい「自己解決能力」が重要です。これは、未知の問題やエラーに直面した際に、他者に頼る前にまず自分で原因を調査し、解決策を見つけ出す力のこと。この能力が高いエンジニアは成長スピードが速く、周囲からの信頼も厚くなります。
現場では、日々新たな課題や予期せぬエラーが発生します。その都度、先輩や同僚に質問していては、チーム全体の作業効率を下げてしまう可能性があります。
もちろん、どうしても解決できない問題や、チームの方針に関わる重要な判断は相談が必要ですが、その前段階として「自分でできる限りの調査と試行錯誤を行う」という姿勢が、エンジニアには不可欠です。
では、この自己解決能力を大学生のうちにどう養えば良いのでしょうか?以下のポイントを意識するといいでしょう。
⑥ポートフォリオの作成【重要】
大学生の間にやっておくべき最重要なことが、ポートフォリオの作成です。
ポートフォリオとは、自分が開発したサービスをまとめた資料のことです。
エンジニア業界では、学歴や職歴よりもポートフォリオが重視されます。
未経験だろうと、ポートフォリオさえ優れていれば、それだけで人事担当者の食指が動きます。
プログラミングの勉強をする中で、是非自分なりのWebサービスを作ってみてください。
できればそれをWeb上に公開し、実際にユーザーさんに使ってみてもらってください。
「そんなこと言われても、未経験の状態からじゃどんなサービスを作って、どんなポートフォリオにすればいいのかなんてわからない!」
こういった方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、以下の記事を参考にしていただければと思います。
新卒でWebエンジニアとして就職するために必要なポートフォリオ作りについて詳細にまとめてあります。
Web系エンジニアとして就職する際の会社選び
Web系エンジニアに限りませんが、就職の際にただ適当に会社を選ぶというのは危険です。
自分が何をしたいのか、どこを目指すのか、ということを視野に入れて、じっくり考えなければなりません。
以下に、Web系エンジニアとして就職する場合の注意点を列記していきます。
Web業界とSI業界の違いを知る
現在のIT業界は、「Web業界」と「SI業界」の二つに大別できます。
■Web業界の企業
インターネットを用いてサービス開発・展開をしている企業
■SI業界の企業
他の会社から案件を受注して開発する企業
プログラムを使って何かを開発する、という点では同じですが、この2つの業界は似て非なる物。
文化や働き方や主な使用言語などが違うため、自分が就職しようとしている企業はどの業界の企業なのか、という部分をしっかり意識してください。
SI業界からWeb業界への転職は難しい
「SI業界の企業に就職しても、何年か経って合わないなと思ったらWeb業界の企業に転職すればいいだけだし、深く考えなくてもいいや」
そうお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。
現在、Web業界とSI業界の分断が進んでおり、途中でWeb業界へ転職したいと考えても、SI業界にいた頃のキャリアが全く評価されないというケースも多々存在するのです。
Webエンジニアとして働きたいと考えている場合は、新卒での就職時にきちんとWeb業界の企業を選ぶようにしてください。
Web業界とSI業界の違いや、企業選びの基準などはこちらの記事に詳しくまとめてありますので、是非お一読ください。
よくある質問
Q. 文系でも不利にならない?
A. 不利になることはありません。前述の通り、企業は学部よりも個人のスキルや熱意を重視します。文系で培った論理的思考力やコミュニケーション能力は、エンジニアの仕事でも大いに役立ちます。実際に文系出身で活躍しているWeb系エンジニアはたくさんいます。
Q. プログラミング未経験ですが、本当にWeb系エンジニアになれますか?また、どのくらい勉強時間が必要ですか?
A. はい、プログラミング未経験からでもWeb系エンジニアを目指すことは十分に可能です。学習時間については個人差が大きく、目標とするレベルによっても異なりますが、一般的にプログラミングの基礎を習得するのに200~300時間、簡単なWebアプリケーションを自分で考えて作れるようになるまでには、少なくとも500~1000時間程度が一つの目安と言われています。
十分な時間の確保がしやすい学生の内からコツコツ勉強しておくのがおすすめです!
Q. 英語はできたほうがいい?
A. 必須ではありませんが、できた方が圧倒的に有利です。プログラミングに関する最新の情報や公式ドキュメントの多くは英語で書かれています。英語が読めると、情報収集の幅が格段に広がり、問題解決やスキルアップのスピードが速まります。まずは技術記事を読むことから慣れていくのがおすすめです。
Q. Web系エンジニアになるために、大学生のうちに取っておくべきおすすめの資格はありますか?
A. Web系エンジニアの就職活動において、資格が必須となるケースは稀です。資格取得よりも、実際に手を動かして作成したポートフォリオ(Webサイトやアプリケーション)や、インターンシップでの実務経験の方が高く評価される傾向にあります。
ただし、基礎知識を体系的に学ぶ目的や、学習のモチベーション維持のために資格取得を目指すのは良いでしょう。その場合は、国家資格である「基本情報技術者試験」や、特定の言語に関する認定資格が挙げられます。
資格取得がゴールにならないよう、そこで得た知識をどう実践に活かすかを常に意識することが大切です。
Q. 新卒からフリーランスは目指せる?
A. 新卒で実務経験がない状態からフリーランスエンジニアとして活動するのは、非常に困難であり、一般的にはお勧めできません。
主な理由として、実務経験がないと高単価な案件を獲得するのが難しく収入が不安定になりやすいこと、スキルアップの機会や相談できる先輩がいないため成長が滞る可能性があること、そして何より貴重な「新卒カード」を活かして企業で体系的な教育や多様な経験を積むチャンスを失うことなどが挙げられます。
ごく一部、学生時代に突出した実績や人脈を築いたスーパーマンのような方であれば可能性はゼロではありませんが、まずは企業に就職して実務経験を積み、技術力とビジネススキルを磨くことが、将来的なキャリアの安定と成長にとって堅実な道と言えるでしょう。
まとめ:大学生がWebエンジニアを目指すなら、バックエンドエンジニアがお勧め
将来エンジニアになりたいと考えている大学生には、Webエンジニアをお勧めします。
特に「Ruby on Rails」を使うバックエンドエンジニアを目指すのがよいでしょう。
その理由は、主に3つ。
■Web系企業では「Ruby on Rails」のバックエンドエンジニア求人数が最多
■Rubyを作ったのは「まつもとゆきひろ」という日本人のため、日本において学習教材が多い
■フロントエンドエンジニアよりも専門性が高いため、収入も高くなりやすい
フロントエンドエンジニアは、比較的歴史の浅い職歴です。
未経験から目指しやすいというメリットはありますが、その分競争率が高く、収入面でもバックエンドエンジニアに劣ることが多いです。
であれば、高度な知識とスキルが要求されるかわりに高収入が期待できるバックエンドエンジニアを目指す方が、将来を考えると得策なのではないでしょうか。
このほか大学生からエンジニアとして就職された方の体験談を以下にまとめてます。ぜひこちらもあわせてお読みください。

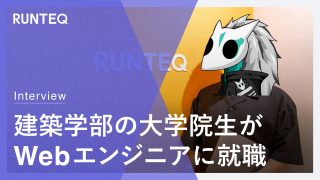
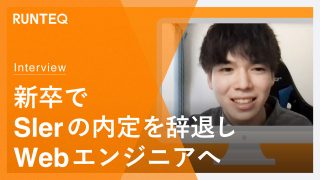
https://runteq.jp/blog/programming-career/graduate/2148/
最後に
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
無料カウンセリングでは、あなたの学習状況や目標を伺いながら、基本情報技術者試験への取り組み方も含め、最適な学習ロードマップを一緒に描きます。
RUNTEQで、確かな一歩を踏み出しましょう!
\ あなたの挑戦を全力サポート! /
無料で話を聞いてみる ▶︎▶︎